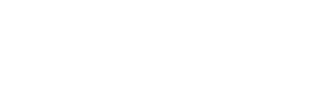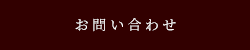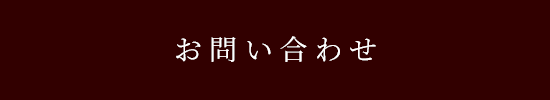トランプ関税でASEANの分断は進むか?国ごとに異なる相互関税率、市場開放やインフラ支援など中国による離間の計も(2025年10月 JBpress掲載)

※2025年10月24日付のJBpressの記事を一部変更して掲載しています。
2025年1月に発足した米国の第2期トランプ政権(トランプ2.0)は、戦後80年間米国主導で築き上げ、維持されてきた国際秩序を大きく変えようとしている。日本を含むインド太平洋地域の経済秩序も、関税措置をはじめとするトランプ2.0の諸政策の荒波にのみ込まれようとしている。変わりゆくインド太平洋経済秩序に日本やASEAN(東南アジア諸国連合)諸国、インド等の同地域諸国はいかなる戦略で臨むべきか。また、同地域でビジネスを展開する日本企業は、これにどう対処し、どのような事業戦略を構築すべきか。
オウルズコンサルティンググループでは、こうした論点を議論するため、「トランプ2.0時代のインド太平洋経済秩序と日本企業への影響」と題し、同地域の政治経済を専門とする有識者との連続対談を企画した。第4回は、これまでの3回の対談にご参加いただいた篠田 邦彦・政策研究大学院大学教授(以下、篠田教授)、椎野 幸平・拓殖大学国際学部教授(以下、椎野教授)、助川 成也・国士舘大学政経学部教授(以下、助川教授)(対談順)と、弊社代表取締役CEO・羽生田 慶介による座談会(10月3日実施)の前編です。(モデレーター: 弊社シニアフェロー 菅原 淳一)
ASEANの米中均衡戦略はうまくいくのか
モデレーター:
3回の連続対談では、「トランプ2.0下のインド太平洋経済秩序と日本企業への影響」をテーマにご議論いただきました。今回は、その中で特に興味深い論点について皆さんのご意見を伺いたいと思います。
このテーマを論じる際に最も注目されるのは、米中対立の中でインド太平洋諸国がどのようにこれに対処するかという点だと思われます。対談では、ASEAN(東南アジア諸国連合)は、米中どちらか一方に付くのではなく、両国の間でバランスをとる米中均衡戦略をとっていくとのお話がありました。しかし、米中双方による圧力や懐柔策によって、これは今後一層難しくなっていくのではないかと思われますが、いかがでしょうか。
篠田教授:
ASEANにとっては中国が最大の貿易相手国である一方、米国がASEANへの最大の投資国です。ASEANの一部諸国は安全保障面においても米国の支援を受けていることからすれば、米中均衡戦略が最も合理的な戦略で、これは今後も変わらないとみています。
ただ、ASEANの中でも国ごとの違いは出てくるでしょう。ベトナムやフィリピンは南シナ海の領有権問題で中国と対峙していますし、他方でカンボジアやラオスは中国からの高速鉄道や経済特区の開発などで中国に経済的に大きく依存しています。また、分野によっても違いがあると思います。例えば、インフラ投資では、一帯一路による中国との連結性強化はASEANにとって重要です。他方、IT(情報技術)分野では、米国のプラットフォーマーがASEANにも進出していますので、企業間協力を深めていくとみられます。
モデレーター:
第2回対談では、ASEANの対米輸出における中国による積み替えや迂回輸出に対する米国の高関税賦課などによって、中国から原材料や中間財を輸入し、域内で最終製品にして米国に輸出するというASEANのビジネスモデルが今後難しくなるとのお話もありました。この点はいかがでしょうか。
助川教授:
厳しくなると思います。日本企業を中心に、現地やASEAN域内での調達を増やす方向に向かうとみています。ベトナムの場合、最大の輸出市場である米国を今後も確保していくということであれば、迂回輸出とみなされて40%もの関税を課せられる状況を回避すべく努力していくでしょう。この状況は、第2期トランプ政権(トランプ2.0)後も大きくは変わらないという前提で考えた方がよいと思いますので、企業にとってサプライチェーンの再編は一考の余地があると思います。
「トランプ1.0以前の世界に戻るという期待は抱かない方がいい」
モデレーター:
トランプ2.0後も米国が以前のような自由貿易志向に戻るか戻らないかは大きな論点のひとつです。トランプ大統領の任期満了までのあと3年強を我慢すればよいのか、その後も関税措置を多用する保護主義的、米国第一主義に基づく政策が続くのかで、企業の事業戦略は大きく変わると思いますが、この点はどうでしょうか。
羽生田:
米国では、政権交代によって政策が大きく転換することはよくあることですが、米国第一主義という政策の方向性はトランプ2.0後も変わらないと思います。バイデン政権も、トランプ1.0の関税措置をそのまま維持しましたし、トランプ1.0以前の世界に戻るという期待は抱かない方がいい。また、企業にとってサプライチェーンの再編は容易なことではありません。トランプ関税に対応するために米国でサプライヤーを育て、現地調達率を高めれば、関税が元に戻ったからといって再び日本や中国から輸入するというわけにはいきません。
モデレーター:
日本企業がASEAN域内での現地調達率を高めるという点での見通しはいかがでしょうか。
椎野教授:
米国による措置がいまだ定かではありませんが、ASEANからの迂回輸出に40%の関税が課せられる、かつ、中国製の部材が少しでも用いられている場合は対象になるという厳格な措置となる場合、その継続が予見可能であれば、日本企業が投資を決断することもあると思います。ただ、その予見可能性は大変低いと思います。輸入価格の上昇によって関税を下げるといった米国の政策変更リスクが相当程度ある中で、生産調整を超えて、大型の追加投資の決断は難しいのではないでしょうか。国による違いもあると思います。ジェトロ調査によれば、タイでの日系企業の現地調達率は6割程度で、中国からの調達比率も低い一方、カンボジアは中国からの調達比率も高く、簡単にはいきません。
インドは米中均衡戦略をとれるのか
モデレーター:
ASEANは、課題を抱えながらも今後も米中均衡戦略をとっていくというお話だったかと思いますが、では、インドはいかがでしょうか。米国とは関税問題などで関係が悪化する一方、中国とは関係が改善しているようにもみえます。
椎野教授:
インドは構造的に均衡戦略をとらざるを得ない立場にあります。中国とは国境を巡る軍事的緊張がある以上、根本的な関係改善はないとみています。また、インドはロシアに対する武器調達の依存を低減しようとしているとみられます。こうした状況では、米国や欧州との関係が決定的に重要となります。
インドは、バイデン政権期に米国とiCET(Initiative on Critical and Emerging Technology:重要・新興技術に関するイニシアチブ)という連携枠組みを立ち上げました。これは、トランプ2.0ではTRUST(Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology:戦略的技術を活用した関係の変革)となりましたが、インドにとって極めて重要な枠組みだと思います。したがって、米国とも何らかの落としどころを探っていくことになると思いますが、その際のレバレッジとして中国との関係改善を利用していくということではないでしょうか。
トランプ大統領の関心が低いQuadと米印関係
モデレーター:
最近では、印中関係はBRICSでの連携等を通じて深まっているようにみえます。他方で、トランプ大統領はQuad(日米印豪)への関心も低く、米印関係は冷めているように感じます。
篠田教授:
インドは、戦略的自律性を外交政策の基本として、米国、中国、ロシア、欧州などと等距離外交を続けてきましたが、米国から50%もの関税を課される一方、9月には上海協力機構首脳会議に参加して中国との距離を縮めました。ただ、同会議前にはモディ首相が訪日して日印首脳会談を行ったり、抗日戦争勝利80周年記念式典には参加しなかったり、日本や西側諸国への配慮がみられます。BRICSの拡大も、インドよりも中国やロシアが積極的であるように思います。
インドは2023年にG20の議長国を務めた際に、AU(アフリカ連合)を招いたり、「グローバルサウスの声サミット」を開催したり、独自のグローバルサウス外交を展開しているようにみえます。Quadは、今秋に予定される首脳会合にトランプ大統領が参加しないのではないかと言われており、結束力が落ちています。また、IPEF(繁栄のためのインド太平洋経済枠組み)も、サプライチェーン協定やクリーン経済協定などが残っていますが、米国は実質的に不参加の状況になっています。その点では、米国抜きでも、インドやオーストラリア等を巻き込んだ枠組みを強化していくことが日本にとっての課題となっています。
モデレーター:
インドは「グローバルサウスの盟主」を自任していますが、こうしたインドの動きをASEANはどのように評価しているのでしょうか。
助川教授:
インドは人口規模も大きく、現在ASEAN・インドFTA(自由貿易地域)の物品貿易協定の改正交渉も行っています。ASEANもインドとは良好な関係を築き、米中に加えて第3のリスクヘッジの国とみているように思います。
椎野教授:
ASEAN諸国は総じて、輸出先の多元化を進めようとしています。インド市場の開拓は、ASEAN各国にとっても中長期的な課題です。シンガポールは既に先駆的な動きをみせています。また、IPEFがどこまで使えるかわかりませんが、日本も含めた形で日・ASEAN・インドのサプライチェーンの強靱化を図っていくことも重要です。
モデレーター:
近年の日本企業へのアンケート調査では、今後の投資先としてインドは上位にあります。日本企業にとって、こうしたASEAN・インド関係はどのようにみえているでしょうか。
羽生田:
インドは、日本企業にとって魅力的な市場ですし、ひと頃よりも魅力が増しています。かつては、マルチスズキ(スズキのインド子会社)を例外として、日本企業は苦杯をなめてきましたが、近年では日本企業もインド市場での戦い方を身につけてきたと思います。ASEAN・インド関係でいえば、在ASEAN企業にとってインドは輸出市場として魅力を増していますが、サプライチェーンとして連結するということには冷めているように思います。ただ、デジタル分野は、マレーシアの半導体製造とインドのソフトウェアなど、現実味が出てきた気がします。
トランプ関税でASEANの分断は加速するか?
モデレーター:
3回の対談で、トランプ関税がASEANの域内統合に与える影響については、少し異なる意見がみられました。米国のASEAN諸国に対する相互関税率が国ごとに異なるものになったことで、ASEAN諸国間で競争条件の有利不利が生じ、競争を生み出すという見方や、トランプ関税への共同対処のために域内統合を促進するという見方がありました。また、トランプ関税はASEAN域内統合にあまり影響を与えないとの意見もありました。これについてはどう思われますか。
篠田教授:
これについては、両方あると思います。トランプ関税によって米国以外に輸出市場を多様化しなければならないときに、ASEAN域内貿易の拡大やASEAN+1FTA(自由貿易協定)の一層の拡充には、ASEANが結束して統合を進めていく必要があります。他方、国ごとにトランプ関税の関税率も対米輸出依存度も異なることは、分断につながるかもしれません。ひとつ懸念しているのは、トランプ関税で悪影響を受けた国に中国が自国市場開放やインフラ整備などで手厚く支援すると、ASEANの中で中国寄りの国と米国との関係維持に努める国とに分かれてしまうリスクがあるのではないかということです。
椎野教授:
対談では、ASEANの域内統合は物品貿易については既に大きく進展しているので、トランプ関税は域内統合を促進する力にはなるけれども、政策手段は相当限定的になるとお話ししました。トランプ関税によって中国は東南アジア諸国への外交攻勢を強めており、方向としては分断に向かう力が働きますが、ASEANが分断されることはないと思います。ASEANの歴史をみれば、小国が外交力を発揮する装置としてASEANという枠組みを使ってきました。そのメリットを域内の国は皆認識しているはずです。ASEAN+1FTAを拡大していくということもあり得るでしょう。
羽生田:
ASEANは関税同盟ではなく、域外共通関税もないので、ASEANが「一つの声」で域外国と交渉することには構造上の難しさがあります。加えて、加盟各国にとってASEANという枠組みの求心力が低下しているのではないかと危惧しています。域内統合が大きく進展し、域外に対してもASEAN+1FTAやRCEP(地域的な包括的経済連携協定)が既に結ばれている中で、かつてほどの統合に対するモメンタムがないようにみえます。 ただ、サステナビリティのような欧州から厳しい要求を突き付けられているところでは、アジアの実情に即したルールを作る必要があるので、「一つの声」にまとまることができるのではないでしょうか。
助川教授:
確かに、注目を集めるほどのインパクトのある統合措置などは少なくなっているかもしれません。そもそもASEANの域内統合は、海外からの直接投資を引き寄せるということが重要な目的のひとつであり、そのために注目を集める必要があったのですが、その点では求心力が少し低下しているかもしれません。
ASEAN諸国がCPTPPに参加するうえでのハードル
モデレーター:
ASEAN+1FTAやRCEPのお話がありましたが、日本はトランプ関税の下で、サプライチェーンの多様化や強靱化のためにCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の活用を考えています。CPTPPに関しては、ASEANの中で参加国(シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイ)と非参加国に分かれているわけですが、今後、非参加国がCPTPPに加入することは期待できるでしょうか。
羽生田:
トランプ関税に関する交渉によって、米国に対して国内市場を大きく開放した域内諸国は、市場開放に対する抵抗感が以前より薄れたのではないかと思います。また、輸出市場の多様化のための選択肢を増やさなければならないという切迫感もあるでしょう。その意味では、ASEAN諸国のCPTPP参加に対する準備は以前より整いつつあるといえると思います。私は、CPTPPは「環太平洋」という枠組みにとらわれず、積極的に拡大していくべきだと考えています。
助川教授:
ASEAN域内で自由化が進展し、トランプ関税を巡る米国との合意で大きく市場を開放したので、物品貿易に限れば、以前よりもCPTPPに参加しやすくなったといえると思いますが、問題は物品貿易以外のところです。 カンボジアやラオスまで含めてCPTPPに参加しようとするのであれば、CPTPPのルールの水準を緩和しなければなりませんが、それは望ましくありません。ルールは維持したまま、既にCPTPPに参加している国とともに、日本が支援していくことが重要ではないでしょうか。
椎野教授:
トランプ関税によって輸出市場の多様化を図らなければならない中で、インドネシアやフィリピン、タイのCPTPP参加へのインセンティブは高まっていると思います。インドネシアはすでにCPTPPに参加を申請していますが、これはプラボウォ政権の外交姿勢が大きく影響していると思います。これまでの政権と異なり、通商政策にかなり積極的で、米国との合意では市場を99%開放することや重要鉱物の輸出規制を解除することを明記しています。9月23日には、EU(欧州連合)との包括的経済連携協定に合意しましたが、こちらでも大変高い水準の自由化を約束しています。CPTPP参加に際して問題になるとみられていた電子商取引分野についても、EUとの合意には先進的な規定が盛り込まれているようです。
ただ、問題は「労働」です。インドネシアには、パームオイル産業での人権問題などがあり、CPTPPの「労働」に関する規定を受け入れられるかが課題です。フィリピンもCPTPP加入への機運が高まっていますが、フィリピンにとっても「労働」は問題でしょう。タイについては、物品貿易でも問題はありますが、一番大きな問題はサービス分野です。タイは依然として、サービス業における外資参入は原則50%未満としていますが、これを緩和することには国内の反対が強くあります。また、各国共通の問題として「政府調達」があります。政府調達市場の開放はどの国にとっても課題となります。
モデレーター:
既にベトナムやマレーシア、ブルネイも参加しているので、ある程度は「例外」によって対応できるかもしれませんが、参加に向けたハードルが高いことは確かですね。CPTPPには、中国が参加申請していますが、これにはどう対処すべきでしょうか。
篠田教授:
中国が参加申請したのは2021年ですので、4年間目立った動きがないのは、日本を含めた参加国が慎重な姿勢を示しているということでしょう。中国の参加によって、高い水準の自由化やルールが骨抜きになることが心配されているようです。また、CPTPPで中国との貿易投資関係が緊密化することで、経済的な相互依存関係が武器化されることへの懸念もあるようです。中国の参加にあたっては、「国有企業」「電子商取引」「労働」などについて、中国がCPTPPの高い水準のルールを受け入れる必要があります。また、過去の閣僚声明には、CPTPPが経済的威圧に対抗するツールであることが盛り込まれていますが、これは中国に対する牽制です。 仮に、インドネシアやタイ、フィリピンの参加の際に広く例外を認めれば、これを中国にどう説明するかは難しい問題になるのではないでしょうか。
羽生田:
トランプ関税で米国市場への参入が難しくなる中、中国がCPTPP参加によって自国市場を大きく開放するということであれば、これを歓迎する参加国もあるのではないでしょうか。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
代表取締役 CEO
羽生田 慶介
関連レポート・コラム
ASEANと中国ではどちらからの輸出が得か、関税地獄の中でFTAをどう活用すべきか…トランプ2.0の負けない貿易戦略(2025年9月 JBpress掲載)
ブロック化する世界の中で重要度が増すCPTPP、瓦解する自由貿易体制を守り抜くために必要なASEANとの連携深化(2025年10月 JBpress掲載)
インド太平洋地域の新たな通商枠組みにおけるデジタル分野のルール形成(2023年2月 月刊アイソス掲載)
続・パワーアップしたタリフマン2.0(2025年7月 JMF経済ニュースレター掲載)
トランプ2.0で経済安全保障はどう変わるか? (2024年11月 JBpress掲載)
2024年地政学・経済安全保障 クリティカル・トレンド(2024年1月 JBpress掲載)
「地政学リスク」とは|事業環境の変化に備える
「トランプ関税」とは|トランプ関税の根拠となる3つの通商法の仕組みと企業対応
「経済安全保障」とは①|日本の取り組みと企業に求められる対応
「経済安全保障」とは②|主要国(米国・EU・中国)の取り組み
グローバルサウスとは |国際秩序を揺さぶる新勢力と日本企業の戦略
IPEF(インド太平洋経済枠組み)とは|交渉のポイント
関連サービス