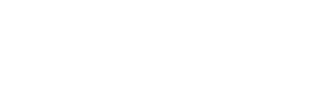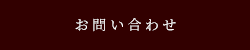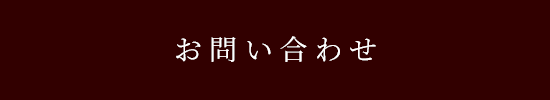ブロック化する世界の中で重要度が増すCPTPP、瓦解する自由貿易体制を守り抜くために必要なASEANとの連携深化(2025年10月 JBpress掲載)

※2025年10月17日付のJBpressの記事を一部変更して掲載しています。
2025年1月に発足した米国の第2期トランプ政権(トランプ2.0)は、戦後80年間米国主導で築き上げ、維持されてきた国際秩序を大きく変えようとしている。日本を含むインド太平洋地域の経済秩序も、関税措置をはじめとするトランプ2.0の諸政策の荒波にのみ込まれようとしている。変わりゆくインド太平洋経済秩序に日本やASEAN(東南アジア諸国連合)諸国、インド等の同地域諸国はいかなる戦略で臨むべきか。また、同地域でビジネスを展開する日本企業は、これにどう対処し、どのような事業戦略を構築すべきか。
オウルズコンサルティンググループでは、こうした論点を議論するため、「トランプ2.0時代のインド太平洋経済秩序と日本企業への影響」と題し、同地域の政治経済を専門とする有識者との連続対談を企画した。第3回は、ASEAN(東南アジア諸国連合)の経済統合や同地域における日本企業の事業活動の分析を専門とする助川 成也・国士舘大学政経学部教授(以下、助川教授)と、弊社代表取締役CEO・羽生田 慶介の対談です(9月26日実施)。
米国史上では自由貿易がむしろ例外
羽生田:
第2期トランプ政権(トランプ2.0)は、世界の多くの国に相互関税を課したり、鉄鋼や自動車などを対象とした分野別関税を発動したり、関税措置を濫用しています。日本を含むインド太平洋諸国にとってはこれにいかに対応するかが喫緊の課題となっています。他方で、これはトランプ政権が「特殊」なのであって、いずれ米国は自由貿易に戻ってくると期待する声もあります。一般的に、経済成長と貿易の間には正の相関関係があり、戦後のGATT(関税貿易一般協定)・WTO(世界貿易機関)体制の下で米国も自由貿易の恩恵を長く受けてきました。米国の自由貿易への回帰の可能性について、どう思われますか。
助川教授:
2022年にダグラス・A・アーウィン著の『米国通商政策史』(長谷川聰哲監訳、文眞堂)の一部を翻訳する機会がありました。米国は来年、建国250年を迎えますが、この本では建国から第1期トランプ政権発足前までの米国の通商政策の歴史を扱っています。多くの方が、米国は自由貿易、多国間主義の国というイメージを持っていると思うのですが、著者のアーウィンによれば、それは第2次世界大戦の直前から日本との貿易摩擦が激しくなる前あたりまでで、米国の歴史全体をみれば、自由貿易の時期の方がむしろ例外であったということです。関税を含めた通商政策は議会の専権事項ですが、今の米国は、共和党・民主党の党派によらず、自由貿易には懐疑的です。米国の保護主義的政策は、トランプ政権の残り3年強で終わるのではなく、長期にわたって続くものと考える必要があると思います。日本企業も、それを前提として長期戦略を立てるべきでしょう。
羽生田:
トランプ政権は、米国内の製造業の保護・育成に力を入れています。これがうまくいけば、輸出に目が向き、自由貿易への回帰も考えるかもしれません。ただ、今の米国に製造業を復活させる基盤があるのか疑問です。生産拠点を作ろうとしても、新たに雇用可能な工場従事者・技術者が不足していることが明らかになりつつあります。「保護主義」といっても、本当の意味で「保護」できているとは思えません。
米国との自由化合意を他の国に広げるという奥の手
羽生田:
トランプ関税の影響についてはどうみていらっしゃいますか。
助川教授:
ASEAN諸国が米国と関税交渉で合意しましたが、その内容は明らかでない点も多くあります。ベトナムやインドネシアは、米国に対してほぼ全品目について関税をゼロにすることを約束したとされていますが、例外品目があるような報道もあり、実際のところはよくわかりません。米国にだけほぼ全品目の関税撤廃を認めることは、FTA(自由貿易協定)という形をとらなければWTO協定違反となります。ベトナムやインドネシア市場で日本製品と米国製品が競合している場合には、日本製品が競争上不利となります。
羽生田:
WTOの根本的な原則である最恵国待遇(MFN)、無差別というところをトランプ政権は土台から変えてしまっています。トランプ関税による競争条件の変化に対して、どのように対応すべきかは日本企業にとって重要な課題です。アパレルなどの一部産業では、こうした変化に機敏に対応して生産拠点を動かすことも可能かもしれませんが、化学など設備投資が大きな分野では難しいでしょう。
助川教授:
現実には難しいだろうと思いつつも、私が考えているのは、各国が米国に対して認めた自由化約束を他のWTO加盟国に均霑(きんてん)する(編集注:同条件を与える)ことはできないかということです。どの国もWTO協定違反となることは望んでいませんし、WTOに訴えられる可能性もあります。そうであれば、米国との交渉結果を国際公共財のようにできないかということです。
羽生田:
それは大変面白い視点ですね。私が経済産業省でEPA(経済連携協定)を交渉していた頃は、通商交渉は前例をベースに積み重ねていく、いわゆるビルディングブロックと捉えられていました。もしも米国との合意が各国の貿易自由化のビルディングブロックとなれば、トランプ関税政策に対する各国からの見方も変わる可能性があります。
助川教授:
もう1点考えているのは、今回の米国との交渉はASEAN諸国にとって果たして成功と言えるのか、ということです。ASEAN諸国の中では、(編集注:対米貿易赤字国で交渉対象ではなかったシンガポールを除き)ベトナムが最初に相互関税率20%で米国と合意しました。これが基準となって、インドネシアやマレーシアなどはこれと同等以上の待遇を得ようと個別交渉で次々とカードを切っていきました。ASEANは米国との交渉では個別国に分断され、連携できませんでした。ASEANは、4月の特別経済大臣会合で米国に対して報復しないという点では合意していましたが、ASEANとしてまとまって交渉することは決めませんでした。
羽生田:
結局、インドネシアなどの多くのASEAN諸国の相互関税率が19%となったのに対し、最初に合意したベトナムは20%で、ほぼ全品目での関税撤廃を約束したにもかかわらず、他国より高い水準となってしまいました。
助川教授:
ベトナムのファム・ミン・チン首相は、米国との交渉はまだ終わっていないと発言していますが、その背景には、米国製品に100%の無税アクセスを容認したにもかかわらず、他のASEAN諸国よりも1%高い関税率となったこともあるでしょう。
中国がASEANで進める「ゼロバーツ」工場の真実
羽生田:
トランプ2.0の下で環境が変化する中で、日本はASEANにどう向き合っていくべきでしょうか。かつては日本に競争力があり、ASEANに対して「指導」するという態度でした。しかし、今や日本の競争力が大きく低下し、ASEANは日本にとってイノベーションのパートナーになったと思います。半導体製造や重要鉱物に関しては、日ASEANは重要なパートナーですし、成長を続けるASEAN市場へのアクセスは日本企業にとって引き続き欠かせません。
助川教授:
確かに、2000年前後とは、日本のASEANに対する見方が変わったと思います。今は、「共創」という言葉に代表されるように、ASEANと一緒にやっていこうという認識になっています。その際に、日本がASEANで長年培ってきた「信頼感」は大きな財産です。日本と組んで一緒にやればウィン・ウィンにできるだろうという安心感がASEAN側にはあります。ASEANの信頼できるパートナーとして、日本はその期待に応えるべきでしょう。タイでは今、中国のEV(電気自動車)メーカーがシェアを伸ばしていますが、そのことがかえって日本に対する信頼を高めています。「ゼロバーツ」工場と言われていますが、中国はタイ国内の工場でも製品の部品から工場の建材まで、ほぼすべてを中国から調達し、タイ国内では何の経済的価値を付加していないとの批判があります。翻って、長年にわたって現地で調達ネットワークを築いてきた日本は違うということで日本への信頼感が高まっている。
羽生田:
第二次世界大戦後、他の地域に比べてASEANが急速に発展できたのは、日本のASEAN支援が「愚直」とも言うべき一貫性をもった産業育成であったことも背景にあるのではないでしょうか。ASEANを収奪することなく、競争力の源泉である技術などを移転してきたことが、信頼につながったように思います。もっとも、これによって日本の一部産業は競争力を失ってしまったのですが。
助川教授:
やはり、現地に投資をして、人材を育成したことが一番大きいのではないかと思います。1970年代には、日本が経済的に一方的に収奪しているとして反日運動もありましたが、日本はこれを反省し、現地に貢献して現地と一緒に成長するというマインドに変わりました。政府開発援助(ODA)と相まって、日本企業による教育投資や人材育成がASEANの成長にうまくつながったと言えると思います。
日ASEAN協力で有望な「防災」と「国際標準」
羽生田:
日ASEAN協力では、中国に対する過度な依存を低減するという意味でも資源に関する協力が重要だとみています。ただ、インドネシアにおけるニッケル開発のように、日本企業がうまく関与できなかった例もあります。
助川教授:
エネルギーでも同様のことが生じています。タイ・カンボジア領海での共同開発も、両国の国境紛争による関係悪化で棚上げ状態になっています。天然ガス開発などにも日本企業が参画していますが、まだまだ十分ではありません。日本政府やJBIC(国際協力銀行)等の一層の支援も必要でしょう。
羽生田:
私が今注目しているのが「防災」です。防災を産業にするという点では、日本にはポテンシャルがあります。ASEANをマーケットとした防災産業というのは、日本にもASEANにもよいと思うのですが、いかがでしょうか。
助川教授:
大変良いと思います。ASEANでも、日本が地震国で、優れた耐震技術を持っていることは知られています。例えば、25年3月にミャンマー中部ザガイン地方で発生した大地震で、1000kmも離れたタイ・バンコクも大きく揺れました。日本でいうと震度3から4程度でしたが、亀裂やひびが入った高層ビルが多数でました。一方で、日本のゼネコンが作った建物はビクともしなかったこともあり、日本の建築基準や建築技術への信頼はますます高まりました。震災後の迅速な復旧に関するBCP(事業継続計画)とか、震災時に役立つ製品とか、防災は日本とASEANが協力できる分野だと思います。
羽生田:
なかでも優先度が高いのは水害でしょうか。フィリピンでの台風による水害などがあります。
助川教授:
タイやインドネシアでは慢性的な洪水リスクに晒されていることに加えて、勢力が増した低気圧で発生する「高潮」と気候変動による「海面上昇」などの問題があります。洪水対策には上下水道の整備が重要になりますが、JICA(国際協力機構)の技術協力の一環として北九州市がカンボジアの上下水道整備に協力した成功事例もあります。こうした日本が培った技術や経験を、リスクを抱える他国に展開していくことが望まれます。
羽生田:
もうひとつ、「国際標準」策定に関する日ASEAN協力はどうでしょうか。日本が今後国際標準戦略を進めていく中で、ASEANのニーズを聞きながら、一緒に国際標準を作り上げていくのは重要ではないでしょうか。
助川教授:
国際標準策定の場でASEANを支援するというのは日本が役立てるところだと思います。国際標準策定では仲間作りが不可欠ですが、ASEANは10カ国、東ティモールの加盟でもうすぐ11カ国になります。日本にとってもメリットがあるでしょう。
自由貿易体制の守護神としての覚悟はあるか?
羽生田:
最後に、今後のWTO体制についてお尋ねします。日本はこれまで、米国主導で作り上げられたWTO体制下で、ルールを守り、体制の維持・強化に貢献してきました。しかし、この体制を米国自身が危機に陥れています。先生は冒頭で、米国にとっては自由貿易の時期の方が例外だとおっしゃっていましたが、裏を返せば、いつの日にか米国が自由貿易体制に戻ってくることがないとも言えません。それまで日本が主導してWTO体制を守るべきと思うのですが、いかがでしょうか。
助川教授:
米国の動向によらず、日本は自由貿易体制を守っていくべきだと思います。WTO体制の価値や有効性を日本はよく理解していますし、それは日本に限りません。米国の支持の有無とは関係なく、日本は他国と連携してWTO体制を支えていくべきでしょう。
羽生田:
米国がWTOルールを無視する中で、中国がこれを非難し、自由貿易の守護者であるかのように振る舞っています。実際、中国の首脳や高官が発信する自由貿易重視のメッセージそのものは、正当性のあるものに聞こえるでしょう。かといって、実際には他国への経済的威圧を加えるなど、通商政策に多くの問題を抱える中国と日本が連携するには課題が残ります。ただ、ASEAN等のグローバルサウス諸国の中には中国を支持する国も少なくありません。
助川教授:
ASEANなどからみると、日本は米国の方ばかり向いている、米国に追随しているように見えます。日本が世界から信頼を得るためには、これを脱しなければなりません。中国に対しても、本当に自由貿易の守護者と自称するのであるなら、WTOルール上問題のある行為を是正するよう求めるべきです。
シンガポールのシンクタンクであるISEASユソフ・イシャク研究所の調査によれば、「自由貿易・多国間主義の擁護者」として、ASEANは自身に次いで中国を挙げています。タイでは中国が首位です。中国が自らを自由貿易・多国間主義の擁護者とするイメージ戦略はASEANでは成功していると言えます。実際には、オーストラリアに対する経済的威圧などを行うなど、行動が伴っていません。日本の方が信頼できるということを行動で示すべきです。同じ調査によれば、ASEAN市民の大国に対する信頼感は、中国は低く、日本が大変高くなっています。しかし、日本が米国に忖度するような行動を続ければ、この信頼も失いかねません。
羽生田:
その点では、日本がCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)においてリーダーシップを発揮していくことが重要だと思います。
助川教授:
WTOが機能不全と言われる中、CPTPPは大変重要だと思います。日本が自由貿易体制を守っていく、その一環としてCPTPPの深化や拡大を図っていくということは望ましいと思います。
羽生田:
そうした日本の行動が、ASEANにおける日本企業の事業活動を後押しすることにもなりますね。本日は大変貴重なお話をありがとうございました。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
代表取締役 CEO
羽生田 慶介
関連レポート・コラム
ASEANと中国ではどちらからの輸出が得か、関税地獄の中でFTAをどう活用すべきか…トランプ2.0の負けない貿易戦略(2025年9月 JBpress掲載)
インド太平洋地域の新たな通商枠組みにおけるデジタル分野のルール形成(2023年2月 月刊アイソス掲載)
続・パワーアップしたタリフマン2.0(2025年7月 JMF経済ニュースレター掲載)
トランプ2.0で経済安全保障はどう変わるか? (2024年11月 JBpress掲載)
2024年地政学・経済安全保障 クリティカル・トレンド(2024年1月 JBpress掲載)
「地政学リスク」とは|事業環境の変化に備える
「経済安全保障」とは①|日本の取り組みと企業に求められる対応
「経済安全保障」とは②|主要国(米国・EU・中国)の取り組み
「トランプ関税」とは|トランプ関税の根拠となる3つの通商法の仕組みと企業対応
グローバルサウスとは |国際秩序を揺さぶる新勢力と日本企業の戦略
関連サービス