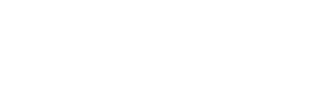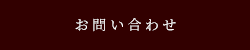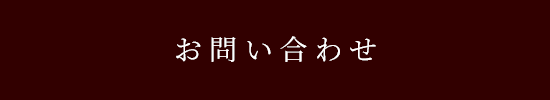ASEANと中国ではどちらからの輸出が得か、関税地獄の中でFTAをどう活用すべきか…トランプ2.0の負けない貿易戦略(2025年9月 JBpress掲載)

※2025年9月20日付のJBpressの記事を一部変更して掲載しています。
2025年1月に発足した米国の第2期トランプ政権(トランプ2.0)は、戦後80年間米国主導で築き上げ、維持されてきた国際秩序を大きく変えようとしている。日本を含むインド太平洋地域の経済秩序も、関税措置をはじめとするトランプ2.0の諸政策の荒波にのみ込まれようとしている。変わりゆくインド太平洋経済秩序に日本やASEAN(東南アジア諸国連合)諸国、インド等の同地域諸国はいかなる戦略で臨むべきか。また、同地域でビジネスを展開する日本企業は、これにどう対処し、どのような事業戦略を構築すべきか。 オウルズコンサルティンググループでは、こうした論点を議論するため、「トランプ2.0時代のインド太平洋経済秩序と日本企業への影響」と題し、同地域の政治経済を専門とする有識者との連続対談を企画した。第2回は、貿易論をベースにインド・東南アジアの政治経済を専門とする椎野幸平・拓殖大学国際学部教授(以下、椎野教授)と、弊社チーフ通商アナリスト・福山章子の対談です(9月11日実施)。
トランプ2.0下でASEAN諸国の「漁夫の利」は続くか
福山:
最初にトランプ関税のASEAN(東南アジア諸国連合)諸国への影響についてお伺いします。第1期トランプ政権(トランプ1.0)では、米国は中国に高関税を課し、ASEAN諸国は「漁夫の利」を得ていると言われました。データからも、ベトナムなどのASEAN諸国からの対米輸出の増大や、米中両国からの対ASEAN投資の増加がみてとれます。第2期トランプ政権(トランプ2.0)では、こうした点も踏まえ、ASEAN諸国を含む世界の多くの国に相互関税が課せられました。現時点でのASEAN諸国に対する相互関税率は、4月の公表時よりは下がった国が多いですが、それでもベトナムは20%、タイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン・カンボジアは19%と決して低くありません。このようなトランプ関税のASEAN経済への影響をどうみていらっしゃいますか。
また、異なる関税率を課せられたASEAN諸国が、自国に有利な環境を築こうとすることでASEANの分断を招くのではないかという見方があります。他方、トランプ関税という共通の課題に対処するために域内経済統合が深まるとも考えられます。こうしたトランプ関税がASEANの経済統合に与える影響をどのようにお考えでしょうか。
椎野教授:
まず、トランプ関税のASEAN経済への影響ですが、ご指摘のように、トランプ1.0では主として中国の幅広い品目に追加関税が課されたため、ベトナムを中心に東南アジア、インドに正の貿易転換効果が生じました。いわゆる「漁夫の利」です。トランプ2.0では、中国以外の国にも幅広く追加関税や相互関税が発動されていますが、中国にも引き続き高関税が課せられています。トランプ2.0では中国に30%の追加関税が現時点で課せられていて、今後引き上げられる可能性があります。これにトランプ1.0時代から多くの品目に課せられている7.5~25%の追加関税が加わります。これに対して、ASEAN諸国に対する相互関税は先ほどご指摘の通りですが、加えて、シンガポールが10%、ブルネイが25%、ラオスとミャンマーは40%となっています。インドに対しては、25%の相互関税に、ロシアからの原油輸入に対する二次関税として25%の計50%の追加関税が課されています。
ここで鍵となるのが中国との関税率差です。タイやマレーシア、ベトナムなどの国と中国との間には、品目によりおおよそ10~45%の関税率の差があります。ジェトロ・アジア経済研究所の試算からは、ASEAN諸国・インドに対する追加的な関税率が10~20%程度にとどまり、中国との関税率の差が40~50%程度ある場合には、ASEAN諸国・インドに総じて正の貿易転換効果が生じることが示唆されています。したがって、今後の米中交渉によって、米国の対中追加関税率がどの程度の水準になるかがASEAN諸国やインドにとって重要になります。また、ASEAN諸国は、トランプ関税に対してそれなりに結束して対応しています。4月のASEAN特別経済大臣会合や5月のASEAN首脳会議では、ASEAN全体としてトランプ関税に対処し、現時点では報復措置は講じないことを確認しています。そうした点では、トランプ関税はASEAN経済統合加速のインセンティブになりえます。
ただ、関税面ではすでにASEAN域内で99%の品目で関税を撤廃しており、関税面での深掘りの余地はほとんどありません。貿易円滑化でも、認定輸出者自己証明制度(ASEAN Self Certification)がすでに導入されていますので、物品貿易に関しては深化の余地は限られます。サービス貿易や電子商取引に関しても、ASEAN域内の課題も多く、加速するかどうかは覚束ない感じがします。他方、AJCEP(日・ASEAN包括的経済連携協定)を含むASEAN+1のFTA(自由貿易協定)には、自由化率の引き上げなど、深掘りの余地があります。
日本企業にとって大きな問題となる「原産地規則」
福山:
家具などの一部分野では、中国企業がASEAN域内に製造拠点をすでに移していて、関税率差の変化に柔軟に対応するのは難しいように思いますが、その点はいかがですか。
椎野教授:
当然、いったん投資してしまったものをそう簡単にサンクコストにして戻すわけにもいきませんので、その拠点を活用していくことになると思います。そのため、今の関税率差でASEANからの対米輸出が可能なものについては継続するでしょう。ただ、中国との関税率差が小さくなる場合には、ASEAN拠点からの輸出を減らし、中国の親会社からの対米輸出を増やすといった生産調整がとられることなども考えられます。その点で、中国企業だけでなく、日本企業にとっても大きな問題は「原産地規則」がどうなるかです。
米国とインドネシアとの合意には「原産地規則」について交渉すること、またベトナムとの合意、7月31日に発令された大統領令には、「積み替え(transshipment)」について明記されています。例えば、(米国での輸入時の)関税率が中国のように高い国の製品が、ASEAN諸国のようにより低い国を経由して米国に輸出される場合には、低い国の関税率ではなく、40%の関税率が課されることになっています。
ただし、「積み替え」の定義が現時点では明確ではありません。米国が今後、FTAで規定される原産地規則やそれ以上に厳しい要件を求めてきた場合には、中間財を中国から輸入することが多いASEAN拠点からの対米輸出に大きな影響をもたらす恐れがあります。重要なのは、関税率差と原産地規則の行方です。
ルール形成ではCPTPPの活用が理想的
福山:
先ほど、ASEAN+1のFTAには深掘りの余地があるとのお話がありました。ASEANと中国の間のFTAであるACFTAはアップデートを重ね、2019年には「ACFTA2.0」が発効しました。「ACFTA3.0」の交渉も完了し、10月の首脳会議での承認を目指しています。AFCFTA3.0には、デジタル経済やグリーン経済、サプライチェーン連結性も含まれており、AJCEPよりも広範な内容に合意しています。
こうした進捗をみると、AJCEPよりもACFTAの方が進化しているようにもみえますが、今年5月の日ASEAN特別経済大臣会合では、AJCEPの活用促進にも言及されているなど、日本政府としてもAJCEPを有効活用したいと考えているようです。今後、AJCEPを活用して日本とASEANの協力を強化して中国に対抗するようなことは考えられますか。
椎野教授:
ACFTAもAJCEPも、ASEAN域内に比べれば自由化率の引き上げなど改善の余地がありますが、デジタル経済やグリーン経済などのルール面ではさほど深掘りはできていないというのが正直なところではないでしょうか。その点は、CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)を活用することが日本にとって最も理想的な形だと思います。インドネシアがCPTPPへの加入を申請しましたが、タイなどの他の国を含め、CPTPPを拡大していくことが日本にとって古くて新しい課題と捉えています。中国や台湾がすでに加入申請しているので、政治的に難しい問題もありますが、これをどのように乗り越えていくかが重要かと思います。グリーン経済に関しては、AZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)の活用が重要で、そこでの協力をFTAにおけるルール形成につなげていくということがASEANを惹きつけるためには望ましいのではないでしょうか。
CPTPPとは異なるRCEPの意義
福山:
AZECについては私も注目していましたので、今後も追っていきたいと思います。今、CPTPPのお話が出ましたが、日本とASEAN諸国が参加するFTAとしてはRCEP(地域的な包括的経済連携)も重要です。RCEPの活用についてはどうお考えですか。
椎野教授:
CPTPPと比べると、RCEPには環境や労働に関する章がありませんし、政府調達も市場アクセスが含まれていません。やはり、ルール面ではCPTPPということになると思います。RCEPは、物品貿易面でのアジア地域のサプライチェーンを支える重要な協定と捉えています。その点では、(交渉の最終段階で離脱した)インドがRCEPに戻ってきてくれることが望まれますが、これは難しそうです。インドにとってRCEPは、多額の貿易赤字を抱える中国とのFTAとなります。また、乳製品がセンシティブ品目である中で、オーストラリア・ニュージーランドに対して市場開放を迫られることにもなります。
今回のトランプ政権との関税交渉でも、米国がインドに乳製品市場の開放を迫っていることが交渉を難しくしています。この2つの問題があるので、インドのRCEP加入は難しいとみています。 ただ、バングラデシュやスリランカなど、他のアジア諸国の加入を促すことによって、ASEANを含むサプライチェーンを支える役割を拡大していくことが次のステップだと考えています。
バングラデシュについては、日本との二国間EPA(経済連携協定)交渉が進んでいますので、そちらの後になるとは思います。香港の加入は、香港を経由した仲介貿易でRCEPを活用できるようになるため利便性が増しますが、政治的な問題が絡んでくるかもしれません。
アジア諸国のFTA締結を後押しするトランプ関税
福山:
FTAの活用という点では、ASEAN諸国やインドによるFTA締結が活発化しています。これは、トランプ関税によって米国以外の輸出先を求める必要が生じたためとみてよいでしょうか。
椎野教授:
インドと英国のFTAが5月6日に急遽妥結と発表されたのは、交渉がかなり難航していましたので、正直驚きました。2016年から交渉していたインドネシアとEU(欧州連合)の交渉も9月中に妥結の方向で調整されています。EUとは、タイやフィリピン、マレーシア、インドも交渉を進めています。
ASEAN諸国やインドと欧州のFTA締結に向けた動きの加速は、トランプ関税の影響によるアジア諸国と欧州との経済関係緊密化の動きの一環とみてよいでしょう。
落としどころが見えない米印の関税摩擦
福山:
ここからは、今までたびたび出てきましたが、インド太平洋地域の重要なプレーヤーであるインドについてお伺いしたいと思います。先ほどお話があったように、トランプ政権はインドに計50%の関税を課し、今秋インドで開かれる日米豪印(Quad)首脳会合にも参加しないと報じられるなど、米印関係に亀裂が生じているといった論調もみられます。他方で、米印は1990年代以降、科学技術、IT・デジタル、宇宙、医薬などの分野での協力も進めてきており、今回の関税賦課を受けても、インドとしては米国との関係悪化を望んでいないともみられています。
また、こうした中で、二国間やBRICSなどの枠組みを通じて、インドが中国に接近しているようにみえますが、椎野先生がかねてご指摘の通り、印中間には長年の政治的問題があり、抜本的な関係改善に至るのは難しいとみられています。インド外交はよく「全方位外交」といわれますが、今後、米国や中国とどのような関係を築いていこうとしているのでしょうか。
椎野教授:
まず、米国との関係ですが、先ほど指摘した乳製品市場の開放問題はインドにとって譲れない一線です。乳製品に関連する雇用は多く、政治的な発言力も大きい。もうひとつの問題はパキスタンとの関係です。今年5月の印パ軍事衝突について、トランプ大統領は自らの仲介で停戦が実現したと主張していますが、これはインドのモディ政権にとっては到底受け入れられるものではありません。今回の軍事衝突の原因でもあるカシミール問題は、印パ二国間の問題だというのがインドの基本的立場であり、第三国の介入を許すことはインド国内の政治問題にも発展しかねません。モディ首相は、米国の仲介を明確に否定しています。計50%という関税もインドにとっては厳しいです。特に、縫製品や履物など労働集約財への悪影響は政治的にもつらいところでしょう。今のところ、iPhoneなどのスマートフォンは例外とされていますが、今後どうなるかは予断を許しません。
ロシア産原油の輸入問題も簡単ではありません。インドにとって、国内の石油小売価格は政治的に極めてセンシティブです。2022年以降、割安なロシア産原油への依存を深めてきており、インドの原油輸入に占めるロシア産原油の比率は4割程度に達しています。これをすべて切り替えることは短期的には容易ではないですが、最近では原油価格が下がってきており、ロシア産原油との価格差も小さくなっていますので、インドがロシア産以外の原油調達を増やす余地はあると考えられ、今後一定の落としどころを探る可能性はあるとみています。
中印関係の改善は経済がベース
椎野教授:
中国との関係は、ご指摘の通り、関係改善によって米国に対するレバレッジを効かせるのは印中両国にとって望ましいことでしょう。ただ、未確定の国境問題を抱え、常に両軍が近い距離で睨み合っているという構造的な問題は変わりませんので、両国の外交関係が根本的に改善することは見込めないと思います。
注目されるのは経済関係です。双方の利害が一致しやすく、互いに歩み寄れる分野を見つけられると考えています。中国側にはレアアースというカードがある一方、インドには中国に対する外資規制やビザのカードがあります。2020年以降、インドは中国からの対内直接投資に対してはすべての投資を個別認可の対象としており、これまでBYDなどの直接投資を認可しなかったとの報道もみられます。この辺りを緩和していく可能性はあるのではないかとみています。
2024年度のエコノミック・サーベイでは、中国からの直接投資について、インドが世界のサプライチェーンに参画する上で重要な役割を果たすと記載するなど、政府内で中国からの投資の受け入れ促進を検討しているようです。製造業振興を掲げるモディ政権にとり、中国からの直接投資がMake in Indiaに寄与するとの考えが出てきても不思議ではありません。
経済安全保障の確保に向けた日印連携強化
福山:
米印、印中の関係は日印関係にも大きな影響をもたらしますが、今後の日印関係をどう展望されていらっしゃるでしょうか。日印間では、半導体など経済安全保障上重要な分野についても産業協力やサプライチェーンの強靱化を進める動きがあります。また、トランプ関税を受けてインドが輸出先の多様化を図る際には、例えば、スズキがインドで生産したEVを欧州に輸出するなど、日本企業が貢献できるところがあると思います。お話では、経済面では印中関係の改善もあるとのことですが、日本の政府、あるいは産業界はインドとどのような関係を築いていくべきでしょうか。
椎野教授:
8月の日印首脳会談では、「日印経済安全保障イニシアティブ」の立ち上げや重要物資のサプライチェーン強靱化などで合意されました。半導体、重要鉱物、医薬品、クリーン・エネルギー、高度人材などが主な協力分野とされています。このうち重要鉱物については、インドにはレアアースを精錬する企業がありますので、日本がレアアース供給の安定化を図る上でインドとの連携が有益だとは思いますが、現状、インドは中国からの輸入に依存していますので、すぐに効果が出るというものではありません。高度人材についても、IT人材の確保は日本にとって重要ですが、日本の高度人材受け入れの制度的障壁が高いわけではないので、マッチングなどできることは限られるように思います。半導体は、インドにとって極めて重要で、国内産業の育成が課題ですので、半導体製造装置や原材料の日本からの対印輸出の安定化や製造人材の育成への期待は大きいと思います。
先ほどお話したように、中国企業が引き続きASEAN諸国やインドに投資する、また、これら諸国と欧州のFTA締結が加速すると、日本企業にとってはASEAN・インド市場における競争が激化していくことが考えられます。他方で、例に挙げられたスズキのケースのように、ASEAN・インドの生産拠点から欧州に輸出しやすくなるという機会も生じます。
福山:
そうした動きが加速するとなれば、いわゆる「米国抜きのFTA」に日本企業としても対応が必要になってきますね。
椎野教授:
シンガポールのリー・シェンロン上級相(前首相)は、貿易においては「全世界」が最善の枠組みだが、一時的には「マイナス・ワン」で進めるしかないといっています。米国抜きでの経済連携が今後加速していくことになるでしょう。これは、米国以外での貿易自由化が進むということですから、日本企業にとっては競争と機会の双方が生じることになります。
福山:
トランプ関税の影響についてお話すると、どうしてもリスクばかりにとらわれがちです。お話を伺って、リスクにはしっかり対処しつつ、機会にも目を向けて対応していくことが日本企業にとって重要だと再認識しました。本日は貴重なお話をありがとうございました。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
チーフ通商アナリスト 福山 章子
関連レポート・コラム
パワーアップしたタリフマン2.0(2025年1月 JMF経済ニュースレター掲載)
続・パワーアップしたタリフマン2.0(2025年7月 JMF経済ニュースレター掲載)
トランプ2.0で経済安全保障はどう変わるか? (2024年11月 JBpress掲載)
トランプ関税で激変するインド太平洋の経済秩序、これから起きる4つの変化に日本人と日本企業はどう対処すべきか?(2025年9月 JBpress掲載)
2024年地政学・経済安全保障 クリティカル・トレンド(2024年1月 JBpress掲載)
バイデン政権の貿易協定やインド太平洋構想(FOIP)等への対応
「地政学リスク」とは|事業環境の変化に備える
「経済安全保障」とは①|日本の取り組みと企業に求められる対応
「経済安全保障」とは②|主要国(米国・EU・中国)の取り組み
「トランプ関税」とは|トランプ関税の根拠となる3つの通商法の仕組みと企業対応
グローバルサウスとは |国際秩序を揺さぶる新勢力と日本企業の戦略
関連サービス