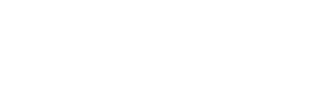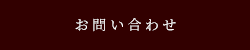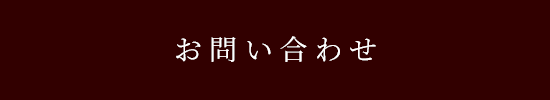トランプ関税で激変するインド太平洋の経済秩序、これから起きる4つの変化に日本人と日本企業はどう対処すべきか?(2025年9月 JBpress掲載)

※2025年9月12日付のJBpressの記事を一部変更して掲載しています。
2025年1月に発足した米国の第2期トランプ政権(トランプ2.0)は、戦後80年間米国主導で築き上げ、維持されてきた国際秩序を大きく変えようとしている。日本を含むインド太平洋地域の経済秩序も、関税措置をはじめとするトランプ2.0の諸政策の荒波にのみ込まれようとしている。変わりゆくインド太平洋経済秩序に日本やASEAN(東南アジア諸国連合)諸国、インド等の同地域諸国はいかなる戦略で臨むべきか。また、同地域でビジネスを展開する日本企業は、これにどう対処し、どのような事業戦略を構築すべきか。
オウルズコンサルティンググループでは、こうした論点を議論するため、「トランプ2.0時代のインド太平洋経済秩序と日本企業への影響」と題し、同地域の政治経済を専門とする有識者との連続対談を企画した。第1回は、インド太平洋協力などを専門とする篠田邦彦・政策研究大学院大学教授(以下、篠田教授)と、弊社シニアフェロー・菅原淳一の対談です(9月2日実施)。
トランプ2.0で生じる4つの変化
菅原:
トランプ2.0の下での米国の政策の変化にインド太平洋諸国は翻弄されています。トランプ大統領は、バイデン前政権が進めた脱炭素やDEI(多様性、公平性、包摂性)の取り組みを撤回し、域内諸国の連携を強化するIPEF(繫栄のためのインド太平洋経済枠組み)からの離脱の意向も示しています。対外援助予算も大幅に削減しました。
こうした政策変化の中で、現在、域内諸国が最も悩まされているのが関税措置です。高関税の脅しをかけられた域内諸国は米国と交渉し、課せられる関税率の引き下げを何とか勝ち取りました。しかし、その代償に、自国市場の開放や米国産品の購入、対米投資などを約束しました。
他方で、中国は米国の措置を保護主義的であると非難し、域内諸国に連携強化を働きかけています。中国からの迂回輸出の阻止を求める米国と、経済関係の強化を求める中国の間で、域内諸国は板挟みになっています。中には、インドのように、米中対立を国益の実現に利用しようとしたたかに立ち回る国もあります。
トランプ2.0の下で変容するインド太平洋地域の経済秩序をどのように捉えていますか。
篠田教授:
トランプ2.0の下で国際秩序がどう変わるのか。これまでの研究を通じて、4つの変化があると考えています。
1点目は、自由貿易体制の毀損です。世界貿易機関(WTO)は、トランプ1.0でも紛争処理制度をはじめとして機能不全に陥っていましたが、トランプ2.0による関税措置、すなわち、従来からの1974年通商法301条や1962年通商拡大法232条による追加関税に加え、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく相互関税によって危機的状況にあります。
2点目は、安全保障に関する米国の関与の低下です。米国は、世界の同盟国に防衛費の負担増を求めています。ウクライナや中東における軍事紛争への関与は、従来の米国に比べれば低下しているようにみえます。仮に、インド太平洋地域でも、台湾海峡や東・南シナ海において力による現状変更が起きた場合、米国を含む西側諸国が欧州・中東・アジアを含む三正面作戦に戦略的に対応できるか危惧する声があります。
3点目は、複合的危機に対応した国際公共財の提供からの米国の撤退です。例えば、気候変動問題を議論するパリ協定からの離脱、世界保健機関(WHO)からの脱退、米国際開発庁(USAID)による対外援助の打ち切りなどです。米国が手を引いたことで生まれた空白を中国などの他の権威主義国が埋めていくリスクが生じています。中国は、香港に国際調停院を設立したり、9月の上海協力機構(SCO)首脳会議で新たな開発銀行の設立を発表したりしています。
4点目は、民主主義・ガバナンスの危機です。米国などの先進国で、グローバリゼーションの進行による格差拡大、社会の分断が生じています。米国では、DEI施策の撤回、移民や留学生の制限なども行われています。米国際放送(VOA)の大幅縮小などもあり、米国のソフトパワーの低下が見込まれます。他方、中国は、「一帯一路」構想等を通じた国際公共財の提供と合わせ、「人類運命共同体」を掲げてグローバルサウスの国々を取り込むなど、自らの影響力(「話語権」)の拡大を図っています。
米中均衡戦略で対処するASEAN
菅原:
ご指摘のように、4つの点において米国が手を引き、それで生じた空白を中国が埋めようとしているようにみえます。SCOやBRICSの拡大などは、それがグローバルサウスの一部の諸国から支持されていることの表れかと思います。ただ、これはインド太平洋地域において、中国が米国に取って代わるということではないと思います。例えば、人民元決済圏の広がりも限定的です。米国と中国のせめぎ合いが今後も続き、そこに域内諸国が巻き込まれていくという構図はしばらく続くように思います。他方で、米中の電撃和解の可能性はどうでしょうか。米中の関税交渉では、追加関税は一時145%に達しましたが、その後引き下げられました。中国がレアアースの輸出管理を緩和し、米国が対中半導体規制を緩和するといったディールも行われています。
米中が和解に転ずるのはいいのですが、それが第三国の犠牲の上に成り立つのでは困ります。ウクライナ情勢を巡る米ロ関係をみていると、そうした可能性を否定できないようにも思えますが、今後の米中関係をどうみていますか。
篠田教授:
かなり難しい質問ですが、トランプ関税の副作用はみていく必要があります。
4月2日にトランプ大統領が相互関税を発表した際には、株と債券と為替のトリプル安となりました。物価も今後上昇するとみられ、国内経済状況が悪化すれば、来年秋の中間選挙に影響が出るでしょう。したがって、米中の貿易政策については、両国経済を大きく毀損しないレベルに持っていくというシナリオが十分考えられると思います。ただし、中長期的には、米中の追加関税を通じた貿易摩擦や半導体・重要鉱物・蓄電池等を巡る技術覇権競争は今後も継続するのではないでしょうか。
菅原:
そうした中で、ASEAN諸国は米中の間で揺れ動いているようにみえます。近年のASEAN諸国の有識者調査では、米中いずれかを選ばなければならない時にどちらを選ぶかという問いへの回答は拮抗しています。中国の南シナ海での軍事的威圧への懸念や、ガザ情勢を巡る対米感情の悪化など、ASEAN諸国でも国ごとに意見が異なります。
また、インドは、先程も述べたように、中国をけん制するために米国に接近したかと思えば、関税措置を巡って対米関係が悪化する中で、中国との関係改善に動いています。米中対立下で、域内諸国は今後どのように対応していくと思われますか。
篠田教授:
ASEANは、米中の対立下において、米中どちらかを選択することを避ける均衡戦略をとっています。その大きな理由のひとつは経済です。ASEANにとり、中国は貿易相手国として長年首位である一方、米国は最大の対ASEAN投資国です。この密接な経済関係を考えれば、ASEANは米中両国の間で均衡戦略をとらざるを得ません。世界が民主主義陣営と権威主義陣営に分かれた場合、中立的なASEANは貿易転換効果の恩恵を受けて経済的にはプラスになるとの試算もあります。指摘された有識者調査では、2024年は米国よりも中国に付くとの回答がわずかに多かったのですが、2025年には逆転しました。ただ、トランプ2.0となって、次の調査では米国に付くとの回答が減るのではないかとみています。
トランプ関税に対処する4つの戦略
菅原:
ASEANにとって均衡戦略は重要であり、今後も継続するとのご意見は同感ですが、今後難しい局面も出てくると思います。例えば、トランプ関税です。米国は、ASEAN諸国に中国からの「迂回輸出」を阻止するよう迫っています。何をもって「迂回輸出」とするかがいまだ不明確ですが、ASEAN諸国が中国から原材料を輸入し、国内で加工して最終製品を米国に輸出するということは今よりも難しくなるでしょう。これは、ASEANの均衡戦略を難しくするうえに、現地に進出している日本企業の事業にも支障を来すことになるのではないかと思います。これにどう対処すべきでしょうか。
篠田教授:
最近、木村福成先生(注:ジェトロ・アジア経済研究所所長、慶応義塾大学名誉教授)のお話を伺う機会がありました。木村先生は、関税戦争への対応として4つの方向性を示されていました。
第1は、関税差を利用してプラスの貿易転換効果を狙いにいく戦略です。米国のASEAN諸国への相互関税は、対中関税に比べれば低いことが多く、有利な立場にあります。
第2は、輸出仕向地の分散化です。ASEAN諸国は現在、米国以外の国との関係強化を進めています。すでにあるRCEP(地域的な包括的経済連携)やCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)、ASEAN+1のFTA(自由貿易協定)に加え、EU(欧州連合)やグローバルサウス諸国とのFTA締結も進めています。
第3は、外国製品、特に中国製品の自国市場への大量流入への対処です。中国も、トランプ関税や国内の過剰供給問題に対処するため、米国以外の市場への輸出を拡大しており、ASEANへの輸出も増えています。これに対抗するため、WTOで認められた貿易救済措置(セーフガード、反ダンピング措置、補助金相殺措置)を準備するということです。
第4は、関税障壁を回避するための直接投資の拡大です。ASEAN諸国でも、トランプ関税を回避するための対米投資が今後増えるかもしれません。
菅原:
今の4つの戦略は、日本にとっても重要ですね。貿易転換効果の点では、日本への相互関税率は15%となり、EUや韓国と同率になりましたので、対米輸出ではそれらの競合国と公平な競争条件が確保できたということになります。輸出先の多様化では、日本もCPTPPの活用や新規EPA(経済連携協定)の締結に向けて動き出しています。また、EUやカナダなどがすでに中国製品に対する貿易救済措置を発動している中で、日本も同様の対応が必要になると思われます。対米投資については、すでに日本は最大の対米投資国ですが、米国との関税交渉合意で5500億ドルの「投資」について約束していますし、今後さらに増えていくでしょう。
基本は米国との関係緊密化と第三国との連携強化のダブル・トラック
菅原:
米国市場は今後も日本企業にとって最重要市場のひとつなので、今のお話は大変有益だと思います。他方で、輸出先の多様化という点にもつながりますが、今後は対米依存度の低減についても考える必要があるのではないでしょうか。これまで日本は、経済安全保障確保の観点から、経済安全保障推進法などを使って国内産業を育成したり、IPEFなどでサプライチェーンの強靱化を図ったりして、中国への過度の依存を回避して戦略的自律性を高めることに努めてきました。トランプ2.0の米国第一の政策の下で、米国にも依存しすぎないことが重要なのではないでしょうか。その意味では、CPTPPなどを活用して米国抜きのフレンド・ショアリングの構築を進めるべきだと思いますが、いかがですか。
篠田教授:
そこは、ダブル・トラックで考えるべきです。
米国とは、貿易転換効果の恩恵を得るために、自動車関税も含め、できる限り低い関税率を確保する。また、対米投資の約束についても、経済安全保障上重要な分野において、日米がともに利益を得られるような強靭なサプライチェーンを構築するために、日本の政府系金融機関が出資・融資・融資保証を行うことに合意しています。米国との関係は今後も緊密化を図るべきです。他方で、トランプ関税などによるリスクをヘッジするために第三国との連携強化も必要です。先ほどお話に出たCPTPPやRCEPなど既存のFTAを活用した内容の深掘りやスコープの拡大、グローバルサウス諸国との新たなFTAの締結を進めていくべきでしょう。
先日のTICAD(アフリカ開発会議)では、日本とアフリカ諸国とのFTAの可能性を今後追求していくことになりましたし、GCC(湾岸協力理事会、注:サウジアラビア等、中東6カ国で構成)とのFTA締結交渉も進められています。IPEFも、すでに発効しているサプライチェーン協定やクリーン経済協定等を活用して、伝統的なFTAではしっかりカバーできていなかった分野での協力を強化していくことが重要です。
中国とはデカップリングではなくデリスキング
菅原:
日本は、今後も中国と建設的な関係を維持・強化していくことが重要で、RCEPを活用すべきだと思う半面、対中依存度の低減とは逆方向の動きともなりえます。この点はどうお考えですか。
篠田教授:
RCEPは、日本と中国の間の唯一のFTAですので、これを活用すべきだと思います。RCEPを通じて、さらなる市場開放を求めたり、環境や労働、国有企業に関するルールを盛り込んだりしていくことを検討すべきです。また、スリランカ、チリ、香港が加入申請しているので、メンバーも拡大してグローバルサウス諸国へのアクセスを確保していくことも重要です。中国との問題はなかなか難しいですが、デカップリングではなく、デリスキングを追求するということだと思います。経済安全保障上の理由から何らかの形で貿易を制限しなければならないところがあるので、そこはきちんと線引きをした上で、自由化を進めるところは進めていったらいいと思います。実際、中国には、日系企業が1万3000社、日本企業の拠点が3万ぐらいあります。日本企業の中国におけるプレゼンスが大きいことに加え、中国での収益は他国に比べてもかなり高くなっています。日本経済の成長のために、中国との関係は切っても切れないのではないかと思います。
サプライチェーンの再編は中長期的に進行
菅原:
次に、日本企業の事業戦略への影響について伺いたいと思います。トランプ関税で言えば、これまでは関税率も定まらない中で、輸出企業が関税コストを負担するケースが多くみられましたが、関税率も定まり、今後は製品価格への転嫁やサプライヤーによる一部負担なども広がっていくとみられます。一部企業は、米国拠点での生産増や対米新規投資、調達先の変更といったサプライチェーンの再編に取り組むものと見込まれます。インド太平洋地域の経済秩序が変わっていく中で、日本企業がとるべき戦略についてどうお考えですか。
篠田教授:
サプライチェーンの再編は自社だけでなく、サプライヤー企業の関与も必要なので短期的には難しいと思います。既存の生産拠点での生産調整や、ポートフォリオの変更といった形で進むのではないでしょうか。ただ、中長期的には、進んでいくことが考えられます。米国との経済安全保障や関税といった問題だけでなく、これまでのChina+1のように、中国での人件費の上昇、ASEANや他のグローバルサウス諸国市場の拡大といった理由によって進んでいくものとみています。
米国第一の政策はトランプ後も継続
菅原:
サプライチェーンの再編といった中長期的な課題に企業が取り組む際には、今生じている変化が今後も継続するのかという点が重要になります。例えば、トランプ関税のような米国の政策は、来年の中間選挙で共和党が敗北すれば転換が図られるのか、次期大統領選挙で民主党の大統領が誕生したら振り子のように以前の世界に戻るのか。企業としては、今後数年だけ耐えればよいのか、中長期的に続くのかで、事業戦略は大きく変わります。米国第一の政策は中長期的に継続するものとみていますが、関税措置の濫用といった手法は大きく変わる可能性もあります。他方、トランプ1.0の関税措置をバイデン政権が変えなかったように、一度発動された関税措置は撤回が難しいとの見方もあります。今後の米国の政策をどのように展望されますか。
篠田教授:
これは本当に難しい問題です。冒頭で述べたトランプ2.0下での4つの変化で言えば、国際公共財の提供に関しては、トランプ1.0からバイデン政権に替わった時もそうでしたが、民主党政権になれば元に戻るのではないでしょうか。パリ協定やWHOに復帰したり、USAIDを通じた対外援助を再開したりすることが考えられます。DEI施策も推進されるでしょう。ただし、関税措置については不透明です。米国内での経済格差や社会の分断の構図が変わらない限り、民主党政権でもいわゆる「忘れられた人々」の声に耳を傾けて政策を進めなければなりません。価値を共有する同志国との連携強化に戻ることは期待されますので、同志国にも高関税を課すような政策は修正されるのではないかと思いますが、国内製造業重視の関税措置や補助金・税制は続いていくと思います。
菅原:
トランプ2.0による分野別関税は今後対象が拡大する見込みですし、米中関係も関税率や規制が厳しくなったり、緩和されたり、まだまだ動きがありそうです。その中で、本日お話しいただいた4つの変化や4つの戦略は大変有益な視点で、重要な示唆をいただきました。本日はありがとうございました。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
シニアフェロー
菅原 淳一
関連レポート・コラム
インド太平洋地域の新たな通商枠組みにおけるデジタル分野のルール形成(2023年2月 月刊アイソス掲載)
バイデン政権の貿易協定やインド太平洋構想(FOIP)等への対応
トランプ2.0で経済安全保障はどう変わるか? (2024年11月 JBpress掲載)
パワーアップしたタリフマン2.0(2025年1月 JMF経済ニュースレター掲載)
続・パワーアップしたタリフマン2.0(2025年7月 JMF経済ニュースレター掲載)
「地政学リスク」とは|事業環境の変化に備える
「経済安全保障」とは①|日本の取り組みと企業に求められる対応
「経済安全保障」とは②|主要国(米国・EU・中国)の取り組み
「トランプ関税」とは|トランプ関税の根拠となる3つの通商法の仕組みと企業対応
関連サービス