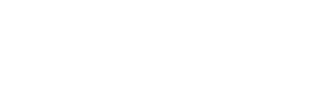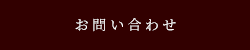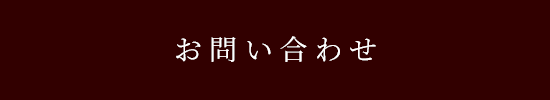※一般社団法人日本機械工業連合会『JMF経済ニュースレター』(2025年7月24日配信)より転載(追記等一部修正)
予測不能なタリフマン2.0
本年1月発刊の『JMF経済ニュースレター』2025年冬号(第145号)に「パワーアップしたタリフマン2.0」という駄文を掲載いただいた。それから半年が経ち、タリフマン2.0は、単にパワーアップしただけでなく、より乱暴で、より予見不能となったことがはっきりとわかった。
中国とは、米国が追加関税を課すと、中国がこれに対抗し、「やられたらやり返す」を地で行く関税合戦となった。一時は米国が中国に対して145%(第2期トランプ政権によるもののみ)の追加関税を課す事態となった。さすがにこれは行き過ぎであり、交渉の結果、一部は撤回、一部は一時停止され、現在は30%となっている。
4月2日には、ほぼすべての国に一律10%、57カ国・地域に個別に設定した国別上乗せ分(日本は14%)の追加関税を課す「相互関税」が公表され、4月5日に一律分が発動された。しかし、株式・債券市場の動揺をみたトランプ政権は、国別上乗せ分については、4月9日午前0時1分に発動したものの、同日13時過ぎに90日間(7/9まで)適用を停止した。
このように、公表した関税措置が金融市場などに悪影響をもたらすと、これをすぐに撤回・緩和することを繰り返したため、トランプ政権の関税政策は「TACO(Trump Always Chickens Out:トランプはいつも怖じ気づいてやめる)」と呼ばれるようになった。トランプ大統領は、これにひどくご立腹のようだ。日本語の「タコ」の意味を知ったら、さらに大変なことになりそうなので、教えない方がよいだろう。
日々変わる関税率だが、第2期トランプ政権発足前には2.4%だった米国の平均実効関税率は、足元では20.6%まで上昇している。これは、スムート・ホーリー法によって関税率が引き上げられた1930年代よりも高い水準だ(イェール大学予算研究所による)。
相手国が繰り広げる「譲歩合戦」
中国、カナダ、メキシコには、不法移民や違法薬物(フェンタニル)の取り締まり強化を求めて追加関税が課せられているが、それ以外の多くの国に課せられているのは、前述の①相互関税一律分(10%)、②相互関税国別分と、③1962年通商拡大法232条に基づく分野別関税の3種である。
米国と交渉している日本を含む各国は、これらすべての追加関税の撤回を望んでいるが、実現は極めて難しいのが現実だ。①相互関税一律分は、米国が貿易黒字となっている英国等にも課されており、連邦政府の歳入源としても期待されているため、撤回は難しい。むしろ、今後引き上げられるおそれすらある。③分野別関税は、現時点では、鉄鋼・アルミ製品に50%、自動車・同部品に25%が課されている。これらは、トランプ政権が目指す製造業の復活と、それによる経済安全保障の確保を目的としているため、撤回は極めて困難だ。こちらも今後、銅や医薬品、半導体等に対象分野が拡大されると見込まれている。
そのため、②相互関税の国別上乗せ分の削減・撤回が各国にとって第一の目標となる。その際、撤回(上乗せ関税率0%)が最も望ましいが、それが無理なら、米国市場における競合国よりも低い関税率まで削減することが死守すべきラインとなる。
これが顕著に表れているのがASEAN(東南アジア諸国連合)諸国の対米交渉だ。4月に相互関税が公表された際、米国が貿易黒字となっているシンガポールを除き、ASEAN諸国にはそれぞれ国別上乗せ分の相互関税が課された。その中で最も低い17%(一律分含む。以下同じ)が課されたフィリピンでは、競合国よりも有利で対米輸出増のチャンスになるとの声も上がっていた。
7月9日の適用停止期間満了を前に、トランプ大統領は8月1日を施行日とする新たな相互関税率を各国に一方的に通知した。この際、4月時点で24%とされていたマレーシアとブルネイは25%に、フィリピンは20%に引き上げられるなどの根拠不明の調整が行われた。
ベトナムは、対米関税の撤廃や第三国(中国等)からの積み替え品への40%の関税賦課などと引き換えに、46%だった相互関税率の20%への引き下げを米国から勝ち取った。「20%」は、のちに米国の対比追加関税率が引き上げられたため、この時点でシンガポールを除くASEAN諸国で最低水準となった。
カンボジアは49%が36%に引き下げられた。その理由は不明であるが、「36%」は隣国タイと同率である。4月と変わらず32%を通知されたインドネシアは、その後19%への引き下げで米国と合意した。この時インドネシア政府は、19%は先に米国と合意したベトナムより低く、ASEAN諸国で(シンガポールを除き)最も低い水準となったことを誇った。その見返りにインドネシアは、米国に対する関税・非関税障壁の撤廃、エネルギーや農産物、ボーイング製航空機50機の購入等を約束したとされる。
このように、各国は米国に大きく譲歩して、競合国よりも低い相互関税率を勝ち取るべく努めた。これは、各国に競わせることでより大きな譲歩を得ることを狙ったトランプ大統領の思う壺とも言えるが、そうとわかっていてもそうせざるを得ない苦境に各国が立たされているということだ。ただ、これらの合意はいずれも詳細が明らかにされておらず、今後の行方には注意が必要だ。
日本が目指す合意ラインは?
日本の対米交渉は難航している。日本政府は当初、上述3種の追加関税すべての撤回を求めて交渉に臨んだようだ。国際ルールに反して米国が一方的に課してきた関税の撤回を求めるのは当然ではある。しかし、残念ながら、現実的な目標ではない。それは、すでに合意に至った英国やベトナム、インドネシアの例をみても明らかだ。
日本はなかでも、対米輸出品目の3分の1以上を占める自動車・同部品の分野別関税の撤回にこだわったようだ。しかし、その実現が不可能に近いことは日本政府もわかっていただろう。低関税輸入枠の設定や、部品での品目別例外を勝ち取れるかがカギとなるとみられるが、これすらも至難の業だ。実際、トランプ政権は、バイデン政権下で認めていた日本に対する鉄鋼の無関税輸入枠を撤廃している。内閣官房でTPP(環太平洋パートナーシップ協定)や日米貿易協定の交渉に関わった渋谷和久関西学院大教授は、日本の対米自動車輸出の約半数に当たる年間70万台に対する関税率10%の低関税輸入枠の設定を提案している(日本経済新聞、2025年7月16日)。これをトランプ大統領に認めさせるだけのカードを日本は用意できるだろうか。
他方、相互関税の削減は何としても勝ち取らねばならない。日本に対する相互関税は、4月の24%から7月には25%に引き上げられた。この引き上げ自体には、キリの良い数字にしたという程度の意味しかないだろう。これを可能なかぎリ10%(一律分)に近づけることが現実的な目標となる。日本政府は、同じく25%の韓国や30%のEU(欧州連合)などの対米交渉の進展を横目でみながら、落としどころを探らなければならない。
8月1日の期限を前に、担当閣僚である赤沢亮正経済財政・再生相は7月21日に8回目の閣僚交渉のため米国に向けて発った。前日に投票が行われた参院選で自民・公明の連立与党は惨敗し、衆参両院で過半数割れとなった。石破茂首相は、続投の理由の一つに日米関税交渉を挙げた。選挙戦では、同交渉について「国益を懸けた戦いだ。なめられてたまるか」と発言した石破首相だが、交渉合意に向けた指導力を発揮できるか。世界の耳目が集まっている。
(2025年7月21日記)
本稿脱稿後、7月22日に米国とフィリピンの交渉が合意に至り、フィリピンに対する相互関税率は20%から19%に引き下げられた。詳細は不明だが、インドネシアと同率となった。
また、日本時間7月23日朝には、日米関税交渉合意のニュースが飛び込んできた。トランプ大統領のSNSによれば、日本への相互関税率は25%から15%に引き下げ、日本は米国に5500億ドルを投資し、日本の自動車・トラック市場、コメを含む農産物市場を開放するとのことだ。
報道によれば、「投資」とは、政府系金融機関による出資・融資・融資保証のことで、対象分野は半導体や医薬品、造船などだという。支援先は米国が選び、利益の9割は米国に配分されるということだ。
すでに関税がゼロである日本の自動車市場の開放は、安全性が担保された米国車の輸入時に追加試験を行わないなど、認証等の手続きの簡素化での合意を指す。コメについては、現在ミニマムアクセスとして輸入している約77万トンは維持し、その枠の中での米国の割合が拡大される。最大の焦点であった米国の自動車関税については、25%の追加関税率が半減の12.5%となり、最恵国待遇(MFN)税率2.5%と合わせて15%となる。この他、米ボーイング社製航空機100機や農産物80億ドル分の購入も日本側は約束したとされている。
「15%」という水準は、企業にとっては痛手であるが、対米貿易黒字国の中で現時点では最低だ。特に、自動車関税の引き下げに合意できたことは高く評価してよいだろう。ただし、今後の米国と他国の合意や、代わりに差し出した日本の提案を精査する必要がある。
(2025年7月23日追記)
株式会社オウルズコンサルティンググループ
シニアフェロー
菅原 淳一
関連レポート・コラム
トランプ2.0で経済安全保障はどう変わるか? (2024年11月 JBpress掲載)
2024年地政学・経済安全保障 クリティカル・トレンド(2024年1月 JBpress掲載)
米大統領選挙戦で加熱する「米国第一」競争~「トランプ化」進むバイデン政権の通商政策(2024年4月 JBpress掲載)
「トランプ関税」とは|トランプ関税の根拠となる3つの通商法の仕組みと企業対応
「地政学リスク」とは|事業環境の変化に備える
「経済安全保障」とは①|日本の取り組みと企業に求められる対応
「経済安全保障」とは②|主要国(米国・EU・中国)の取り組み
関連サービス