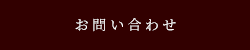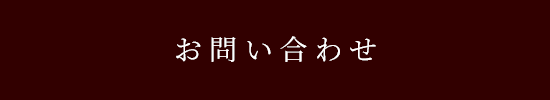「第14回 国連ビジネスと人権フォーラム」の速報レポート(2025年12月 JBpress掲載)
企業活動における人権尊重の取り組みについて議論する世界最大規模の国際会議「第14回国連ビジネスと人権フォーラム(14th United Nations Forum on Business and Human Rights)」が、2025年11月24日〜26日の3日間、スイス・ジュネーブの国連欧州本部で開催された。国連「ビジネスと人権に関する指導原則(以下、指導原則)」が採択された翌年の2012年から毎年続く国際的な議論の場である。
参加者は現地・オンラインを合わせて過去最多の約4650人を記録。うち約3割を企業が占めた。ビジネスからの注目も年々高まっている。
一方で今年の会場の熱量は、昨年と比較するとどこか抑制的で緊張感が漂っていた。昨年は、採択されたばかりのEU CSDDD(企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令)への期待感も相まって、会場全体が熱気に満ちていた。ところが、今年はセッション数や登壇者数が大幅に減少し、参加者間での交流機会も限られた。
背景の一つは国連の財政難だ。今年は米国を筆頭に、英国、フィンランド、フランスなど主要ドナー国が拠出金を大幅に削減し、国連全体の予算は約9000万ドル(約135億円)の不足と報道されている。今年の人権フォーラムの開催規模も縮小となった。参加者間でも「国連の弱体化」への懸念が繰り返し囁かれ、この現実が議論の切迫感を高めていた。またEUの人権関連のルールの簡素化の流れも、人権分野の「後退」の印象を強めていた。
本稿は、フォーラムに現地参加した筆者が、セッションで交わされた議論や会場の空気感を含め、速報として報告するものである。
複合危機時代、人権は「サバイバルモード」に
今年のテーマは“Accelerating action on business and human rights amidst crises and transformations(危機と変革の中で、ビジネスと人権の取り組みをどう前に進めるか)”だった。
会議の冒頭、フォルカー・テュルク国連人権高等弁務官は、“Human rights is on its knees and on survival mode(人権はいま、支えを失い、助けを求めざるを得ないほど追い詰められ、「サバイバルモード」にある)”と述べ、現在の人権状況について痛烈な危機感を表明した。日本にいると実感しにくいが、テュルク氏がここまで強い表現を用いざるを得ないほど世界情勢は危機的状況にある。
議論の中心は「複合危機(Polycrisis)」という概念だ。ロシア・ウクライナ情勢やイスラエル・ガザ等での紛争に伴う地政学的緊張、気候災害の激甚化や、倫理規範が未整備のまま急加速するAI等の技術革新、反DEI・反ESG等の揺り戻しと社会分断等の危機が同時進行している。一つの危機への対応が別問題を悪化させかねず、世界全体の脆弱性の高まりを直視しどう行動を加速させるかが、フォーラムの根幹の問いとなった。
地政学リスクの高まりで問われる「責任ある撤退」
紛争地域・高リスク地域における企業の人権対応に関するセッションでは、「深刻な人権侵害が続き、情報が錯綜する中、企業や投資家はいつどのように事業から手を引くべきか」という難しい判断について議論された。
OHCHR(国際連合人権高等弁務官事務所)が2023年に公表したポジションペーパーでは、「エンゲージメント・オーバー・ディスエンゲージメント(早計な事業撤退や取引停止ではなく、現地に留まり状況改善を図るべきであること)」が基本スタンスとして示されている。
しかし、国家間の制裁などを背景に撤退が避けられないケースもある。この際、企業経営者は撤退を「単なる一点の決断」ではなく、「自社の撤退と、それに伴う影響に従業員や地域社会、取引先が備えられる状態を確保するプロセス」として捉えることが重要だとされた。企業が現地の人権侵害に間接的に関与してしまっていた場合は、完全な撤退後であってもその被害者に対する救済義務を負うという点は、日本企業を含むグローバル企業に突きつけられた重い指摘である。
また今日では、自社が直接加害していなくとも、関連子会社やサプライヤーが深刻な人権侵害に関与していれば、親会社や投資家の責任が問われる。
仏セメント大手ラファージュ社の事例がその象徴として言及された。同社はシリア内戦下で操業を継続する中で、子会社が武装勢力に支払いを行った疑いで訴追された。親会社も資金の流れや意思決定を把握していたとして責任を追及されたのだ。「子会社の判断」という抗弁はもはや通用しない。ミャンマーの情勢に関し、欧州ミャンマー商工会議所(EuroCham Myanmar)のテット・ゾウ・トゥエ氏は、「信頼できる現場情報の欠如」が企業にとって最大の課題だと強調した。インターネット遮断や道路封鎖等が頻発して現地の実態がブラックボックス化し、企業が人権に配慮した事業判断をする上で必要な情報を得ることができないことが、人権DDの大きな障壁となっている。
新疆ウイグル自治区への言及で声を張り上げた中国代表団
会場の空気が一変したのは、中国・新疆ウイグル自治区での強制労働疑義に具体的な言及がなされた直後だ。
会場で参加していた中国代表団が突如声を上げ、新疆の紛争地域指定は誤りであると反発し、強制労働疑惑を「反中勢力による捏造」「事実無根」と全面的に否定し、会場は異様な緊張感に包まれた。その光景は「地政学リスクの高い状況下におけるリスク特定と対応の難しさ」を象徴しているようだった。
高リスク地域においては企業単独の調査には限界がある。だからこそ、企業が市民社会や労働組合と連携し、現場との対話を通して一次情報を共有するマルチステークホルダー連携が不可欠となる。そうして初めて透明性が高まり、実効性ある人権対応が可能となる。
近年の大きな変化として見逃せないのは、ビジネスにおけるAI活用の急拡大である。AIは効率性を高める反面、プライバシーの侵害やアルゴリズムによる差別の助長、表現の自由・政治参加といった権利の制限等をもたらすリスクがあると指摘されている。
議論の中では、「誰が責任を負うのか」という問いが繰り返し投げかけられた。自社がサービスとして利用しているAIが誤った情報を出してしまった場合も、そのシステムを調達・利用した企業が最終的な責任主体とみなされる傾向が強まっている。2024年、カナダの航空会社エア・カナダのAIチャットボットが誤った案内を提供した件で、同社が責任を問われ敗訴した事例が象徴するように、「AIがそう答えたから」という抗弁は法的責任回避の理由にならない。
一方で、AIを単なるリスクとしてではなく、人権DD高度化の「機会」として活用する事例として、米Amazon社の取り組みが紹介された。
同社はかつて、履歴書を自動評価する採用補助AIが学習データの偏りにより女性応募者を不利に扱い、運用を断念した苦い経緯がある。この失敗も踏まえ、現在はサプライチェーン全体の人権DDにおいて、リスクを予測するAIモデルを構築しているという。異常な労働時間やサプライチェーン上の不審な動き、採用パターンデータなどから、人間では見落とされがちなリスク兆候の抽出が可能になった。
同社は、AIの出力を必ず人間の専門家が検証する「Human-in-the-loop」のプロセスを徹底することを強調した。人間による検証は引き続き不可欠でありつつ、AIを「分析を強化する補完ツール」として位置づける姿勢が示された。
気候変動対策が生む新たな問題「グリーン植民地主義」
「気候危機は人権危機」との認識の下、最近耳にする機会が増えた「エコサイド」というキーワードが強調された。エコサイドとは、重大かつ広範な環境破壊を、国際犯罪として問う考え方だ。
EUでは2024年に新たな環境犯罪指令が採択され、加盟国は2026年5月までに、これを国内法に取り込むことが求められている。国際レベルでも、バヌアツ、フィジー、サモア、コンゴ民主共和国などが国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程の改正を正式に提案し、ジェノサイドや戦争犯罪などに続く「第五の国際犯罪」としてエコサイドを追加する議論が進んでいる。これは、環境破壊を企業にとって「刑事責任を伴う犯罪」として位置づけることで、環境影響のリスクの高い案件からの事業撤退等を迫ろうとする動きだ。
また、再生エネルギー開発が先住民族や地域社会に新たな犠牲を強いる「グリーン植民地主義」に陥ってはならないという点も強調された。近年、再エネのインフラ整備が、土地の収奪や暴力、強制移転といった問題を引き起こす事案が指摘されている。先住民族等に影響をもたらす事業においては、FPIC(自由意思による事前の十分な情報に基づく同意)に基づき、権利を尊重するかたちで移行を設計する必要がある。先住民族をただ補償対象・被害者としてではなく、自分たちの事業の対等なパートナーとして位置づけることが重要とされた。
脱炭素に向けた公正な移行の議論では、ラテンアメリカ・カリブ地域を中心に気候アクティビストとして活動する16歳のフランシスコ・ハビエル・ベラ・マンザナレス氏が登壇。「Climate rights is children’s rights(気候の権利とは、すなわち子どもの権利である)」と訴える熱い語り口に、会場からは長く盛大な拍手が送られた。彼の発言は、企業の気候・エネルギー問題への対応は子どもの権利と参加を前提に設計されなければならないというメッセージを、会場の大人たちに突きつけた。
骨抜きになりつつあるEU人権DDルールとその代償
そしてフォーラムの終盤では、この数年急速に進んできた人権・環境DDの義務付けの流れに対し、大きな揺り戻しが生じているとの懸念が議論の中心になった。EUのCSDDD等の簡素化案(オムニバス法案)を巡り、現地では危機感が共有された。とりわけ、EU域内で共通の民事責任ルールを設ける条文の削除や、適用対象企業の大幅な絞り込みにより、多くの人権が救済の枠組みから漏れかねない点が問題視された。このEUレベルでの後退が加盟国に波及し、既に厳しい水準の人権DD国内法を制定済みの国でも簡素化が行われ、EU全体の基準が引き下がるリスクも指摘された。
また、当初案では「直接・間接取引先への能動的な働きかけ等により、情報を網羅的に入手してリスクを特定する」ことが求められていたが、それが「合理的に入手可能な情報」に基づく範囲へと限定された。そのため、企業は、サプライチェーンの奥深くにある「見えにくいリスク」を、あえてリソースを割いてまで特定しようとはしなくなり、本来優先対応すべき深刻な人権リスクが見過ごされてしまう可能性がある。
本来は現場の深刻な状況を改善するための人権DDが、単に手元の書類を確認して終わるだけの「形式的なチェックリスト作業」に成り下がってしまうのではないかと懸念されている。指導原則は、「国家の人権保護義務」「企業の人権尊重責任」「被害者の救済アクセス」という三本柱が補完し合うことで機能する枠組みである。しかし現実には、多くの国で法整備や執行が追いついていない。ルールという後ろ盾がなければ、企業個社の努力には限界があり、真面目に取り組む企業の足を引っ張りかねない。
本フォーラムでは、政府と企業が責任を押し付け合うのではなく、一貫性のあるルール形成を協働して進める必要性が強調された。官民連携が実効性を担保する鍵になるという認識は、登壇者や参加者の多くに共通するものだった。
複合危機を「やらない理由」にしてはならない
フォーラムのクロージングでは、人権理事会副議長のサルマ・ラシード氏が、力強いメッセージで3日間の議論を締めくくった。「Crises should not slow progress. They should sharpen our resolve. (危機は前進を止める理由ではなく、むしろ前進への決意を研ぎ澄ます契機となる)」
今年も、人権侵害の最前線で声を上げ続けるライツホルダーや人権擁護者(Human Rights Defenders)が、企業や政府に耳の痛い問いを投げかけ続けた。彼らが直面する危機の深刻さと、困難に屈せず歩み続ける姿勢が共有されていたからこそ、危機の只中にあっても前進する覚悟を求める副議長のメッセージは会場の強い共感を呼んだ。では、この複合危機と規制の揺らぎが進む不確かな時代に、日本企業はどう動くべきか。
AI活用や脱炭素化が急速に進む一方で、その裏側では新たな人権リスクが顕在化している。結果として、企業の責任範囲は拡大し、複雑化しているのが実情だ。サプライチェーン管理はもとより、AIの倫理的利用や事業撤退時の対応、環境対策と人権のトレードオフなど、今後はより複合的な視点に基づいた事業検証が不可欠となる。こうした複雑な課題に対し、規制の揺り戻しといった短期的な動きに翻弄され、取り組みの軸をぶらすことは、かえって経営の安定性を損なうリスクとなり得る。
危機の時代、1社単独での解決は困難だ。だからこそ、マルチステークホルダーとの連携を深め、大局観を持って人権尊重を経営の根幹に据え続けること──。それこそが、不確実な世界を生き抜くための、確実な投資となるはずだ。来年は指導原則採択から15周年の節目の年となる。危機を「やらない理由」にするのではなく、「決意を研ぎ澄ます」機会に変えられるか。その実践が、今問われている。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
シニアコンサルタント
高橋 夏実
関連レポート・コラム
【第11回国連ビジネスと人権フォーラム 速報レポート】ライツホルダーと共に歩むべき「ビジネスと人権」の次の10年 (2022年11月 JBpress掲載)
「第13回 国連ビジネスと人権フォーラム」の速報レポート(2024年12月 JBpress掲載)
「人権DD」とは|基本的なプロセスとポイント
「ビジネスと人権」とは|指導原則のポイントと国際的な動向
「人権リスク」とは|グローバル企業の事例から見る課題
関連サービス