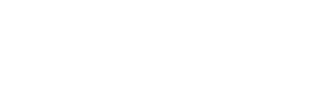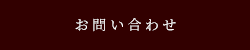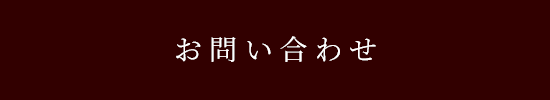市場の重心が東から西に移るインド太平洋地域、ASEAN投資で日本を上回る中国、日本政府と企業はいかに戦うべきか?(2025年10月 JBpress掲載)

※2025年10月24日付のJBpressの記事を一部変更して掲載しています。
2025年1月に発足した米国の第2期トランプ政権(トランプ2.0)は、戦後80年間米国主導で築き上げ、維持されてきた国際秩序を大きく変えようとしている。日本を含むインド太平洋地域の経済秩序も、関税措置をはじめとするトランプ2.0の諸政策の荒波にのみ込まれようとしている。変わりゆくインド太平洋経済秩序に日本やASEAN(東南アジア諸国連合)諸国、インド等の同地域諸国はいかなる戦略で臨むべきか。また、同地域でビジネスを展開する日本企業は、これにどう対処し、どのような事業戦略を構築すべきか。
オウルズコンサルティンググループでは、こうした論点を議論するため、「トランプ2.0時代のインド太平洋経済秩序と日本企業への影響」と題し、同地域の政治経済を専門とする有識者との連続対談を企画した。第5回は、これまでの3回の対談にご参加いただいた篠田 邦彦・政策研究大学院大学教授(以下、篠田教授)、椎野 幸平・拓殖大学国際学部教授(以下、椎野教授)、助川 成也・国士舘大学政経学部教授(以下、助川教授)(対談順)と、弊社代表取締役CEO・羽生田 慶介による座談会(10月3日実施)の後編です。(モデレーター: 弊社シニアフェロー 菅原 淳一)
今後の論点は既にあるRCEPをいかに活用するか
モデレーター:
中国のCPTPP (環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)参加問題は、同様に参加申請している台湾の扱いや、将来の米国の復帰可能性など、論ずべき問題が多くありますので、日本としても対応が難しい面があります。その点では、既に中国もASEAN諸国もすべて参加しているRCEP(地域的な包括的経済連携協定)をどう活用していくかというのが重要な論点だと思いますが、これはいかがでしょうか。
助川教授:
トランプ2.0下で世界の経済秩序が乱されている中で、自由貿易を維持していくためにRCEPを活用すべきです。特に、インドにRCEPに戻ってきてもらうことが重要だと考えています。もちろん、対中赤字の問題、オーストラリア・ニュージーランドの乳製品の問題などを考えれば、インドのRCEP復帰は非常に難しいと思いますので、可能かどうかはわかりませんが、分野別参加を認めることを検討してはどうでしょうか。物品貿易は難しくても、サービス分野ならインドはRCEPに参加するのではないか。それは、アジアで自由貿易の潮流を再び動かすきっかけになります。
椎野教授:
分野別参加は選択肢のひとつかもしれませんが、これを認めると、今後の参加国がいいとこどりする虫食い状態になってしまいかねません。RCEPは、自由化やルールの水準はCPTPPに比べて低く、比較的入りやすいので、一括受諾(全分野参加)で参加国を拡大していくのがよいと思います。
インドについては、トランプ関税で50%を課せられています。これが恒常化するとなれば、RCEPに参加してもよいのではないかという議論が出てきてもおかしくはないです。ただ、政権与党のインド人民党(BJP)を支える民族奉仕団(RSS)の関連機関等が、RCEP交渉時に参加に強く反対しましたので、依然参加へのハードルは高いと思います。
篠田教授:
インドにとっては、RCEPに中国が参加していることが、経済的にだけではなく、政治的にも難しいようです。インドでは、RCEPに入るくらいなら、CPTPPに入る方がよいという議論も聞きました。参加申請しているスリランカやバングラデシュがRCEPに加入すれば、相対的に不利になるインドの加入を促すことになるかもしれません。RCEPでは、5年ごとに行われる「一般的見直し」が2027年に予定されています。日中間や日韓間の関税撤廃率は80%台にとどまっていますので、これを引き上げたり、既存のルールを深掘りしたり、サプライチェーンや環境・労働などの新たなルールの導入を検討したりすることが論点として考えられます。
助川教授:
RCEPの経済的インパクトが小さいのは、関税撤廃までの期間が20~25年とあまりにも長すぎることがあると思います。韓国と中国の間では35~36年です。これを一般見直しなどの機会を利用して短縮できれば利用も増大し、RCEPの求心力が高まると思います。
米国撤退の空白を埋める中国と日本の役割
羽生田:
RCEPの活用というと、対中依存度が高まるとの懸念が示されることがありますが、「対中依存」とはどういうことかはしっかりと考えなければなりません。例えば、レアアースなどの重要鉱物について中国に依存するというのは、採掘・精錬が中国で行われ、中国のコスト競争力も高いという状況では、通商協定の有無によらず、中国に依存せざるを得ません。また、中国の過剰生産による対日輸出の増大についても、これにどう対応するのかは日本の産業政策や成長戦略ともあわせて考えなければなりません。旧来の通商政策の枠組みの中だけで考えていてはいけないと思います。
篠田教授:
中国への市場アクセスということでは、RCEPに加えて日中韓FTAをどうするかも考えなければなりません。 私がRCEP交渉を担当していた際には、80%台にとどまった関税撤廃率や、高い水準のルールができなかった電子商取引や知的財産分野などを含め、RCEPで積み残した問題は日中韓FTAで議論しようということでした。しかし、中国の過剰生産による対日輸出の増大への警戒などがあって、日本としても日中韓FTAには慎重な姿勢を示しているようです。ただ、日中韓FTA交渉を通じて、中国がCPTPPの高い水準の自由化とルールに対応できるかを見定める機会にもなると思うので、日中韓FTAも選択肢のひとつとして残しておくべきだと思います。
羽生田:
日韓経済はもっと密接に連携すべきだと考えています。両国とも現状の産業競争力に対する危機感は高いですし、半導体など相互補完できる産業も少なくありません。また、中国の過剰生産による大量輸出に負けないロボティクスなどの高付加価値の製造業で日本は戦うべきだと思います。
モデレーター:
これまで議論してきた状況下で、日本はインド太平洋経済秩序を再構築するためにどのような役割を果たすべきでしょうか。また、ASEAN諸国やインドは日本に何を期待しているのでしょうか。
篠田教授:
対談では、トランプ2.0の下で国際秩序がどう変わるのかについて、4つの切り口があるとお話ししました。自由貿易体制の毀損、安全保障に関する米国の関与の低下、国際公共財の提供からの米国の撤退、民主主義・ガバナンスの危機です。このうち、これまで議論してきた貿易に関しては、WTOの機能強化や、CPTPPの拡大・EUとの連携といった貿易の多元化のための広域FTAの構築などで日本はリーダーシップを発揮できると思います。
もうひとつは国際公共財の提供という点です。米国はトランプ2.0になってから気候変動に関するパリ協定から離脱したり、WHO(世界保健機関)から脱退したり、あるいは、USAID(米国際開発庁)による資金支援停止、国際機関への拠出金の減額など、グローバルな課題解決でプレゼンスを低下させています。その空白を埋める形で、中国は一帯一路やグローバル開発イニシアチブなどさまざまな取り組みを進めています。本来であれば、米国の撤退による空白を日本や西側諸国、グローバルサウスの国々が協力して埋めていかなければなりません。日本は、欧米先進国とアジア諸国の懸け橋としての役割を果たすべきです。
通商政策をマーケティングのプロダクトと捉えるという視点も
篠田教授:
先ほどサステナビリティの話がありましたが、AZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)のように、化石燃料への依存度が高いアジア諸国において、欧州が進める急進的な再生可能エネルギーの導入のようなものではなく、トランジショナルなエネルギーの転換を進めるような協力をしていくことで、ASEANやインドをひきつけていくことができると思います。
助川教授:
ASEANは、インド太平洋における自らの中心性を認めてほしいと思っています。日本に対して期待しているのは投資であり、技術支援です。米国主導の制度が機能不全に陥っている中で、その穴を埋めてほしいという期待があると思います。RCEPやCPTPPに参加したいものの、能力が追い付かない国もあります。こうした諸国に技術支援や人材育成など、そうした国が参加できるよう日本が支援すべきです。
椎野教授:
インドが日本に期待することのひとつは、AZECのようなエネルギー分野における技術支援とファイナンスだと思います。インドは、太陽光発電では2010年代半ば以降大きく伸びていますので、グリーン水素などに関する協力への期待があると思います。もうひとつは経済安全保障で、特に半導体です。半導体産業の育成を図っている中で、半導体の原材料や製造装置の日本からの安定的な輸入確保に対する期待があると思います。加えて、半導体製造で重要な水の問題です。日本だけでは難しい面もあると思いますが、こうした期待があります。
モデレーター:
日本に対しては、経済秩序の再構築におけるリーダーシップというよりも、目の前の課題に対処するための技術支援や資金援助が期待されているということでしょうか。
羽生田:
いつか米国が自由貿易に戻ってくるまで、日本が旗頭としてこれを守るのだということもあるとは思いますが、日本の通商政策も新たな段階に入る必要があるのではないでしょうか。つまり、一括受諾型の広域FTAの締結のようなホリスティック(網羅的)なアプローチではなく、焦点を絞った課題解決型のアプローチを検討すべきだということです。網羅的でなくても、重要課題をしっかり解決するというところでリーダーシップを発揮できます。また、通商政策をマーケティングのプロダクトと捉えるという視点も重要ではないかと思います。例えば、「重要鉱物」や「水資源」などサプライチェーン上の課題解決や、経済安全保障視点も含めた循環経済の実現など、これまで通商政策が十分価値を発揮できてこなかった分野はまだあります。
篠田教授:
国際秩序作りにおいて、日本がリーダーシップを発揮しないということではないと思います。今は、昔のように米主導のブレトンウッズ体制とか、ワシントン・コンセンサスがあるということではなく、イシューごとに同志国が集まってさまざまな枠組みが構築されています。そうしたさまざまなマルチラテラル、ミニラテラルな枠組みを組み合わせながら国際秩序を形作ることを主導していくのが、日本が今後目指すべき役割ではないでしょうか。
羽生田:
産業界としても、国際秩序作りを主導するというところと、賞味期限の来る前に成果を出すというところと、両面を期待したいです。
日本企業の今後の事業戦略はどうあるべきか
モデレーター:
最後に、このように事業環境が激変する中で、日本企業がとるべき事業戦略はどのようなものでしょうか。
椎野教授:
トランプ関税がひとつの引き金となって、ASEAN・インド市場では中国からの輸出や投資が増えるため、日本企業は中国企業との競争や協調に対処しなければなりません。また、ASEANやインドと欧州諸国などとのFTAが進んでいく可能性が高いと思います。先に述べたインドネシアとEUのFTAや、インドと英国のFTAが最近合意に至っています。インドネシアとEUの合意は、他のASEAN諸国やインドとEUの交渉にも影響を与えるでしょう。今後、ASEAN・インド市場での欧州企業との競争と協調、ASEAN・インドから欧州への輸出機会の増大などに対応する必要があると思います。対米輸出という点では、米国の対中関税率がどうなるのか、それによってASEAN諸国との関税率差がどの程度になるのかが重要です。
また、米国の相互関税には、多くの適用除外品目があります。半導体等の分野別関税が未発動のため、ASEAN・インドからの対米輸出における適用除外品目は結構多くなっています。自社製品がこれに該当するのか、見極めなければなりません。さらに、USMCA(米墨加協定)に基づく特例措置が適用されるメキシコとの比較において、ASEAN諸国が有利となるかどうかも検討する必要があるでしょう。
助川教授:
ASEANにもインドにも相当程度の日本企業の集積ができてきていますので、ASEANとインドをひとつの地域としてみることが重要だと思います。距離の問題、両者間での分業の問題なども含め、ASEANとインドを一体的に捉えたサプライチェーンの構築を考えるべきだと思います。アンケート調査結果から、ASEANからインド市場を狙いたいという企業が相当数出てきています。インドでも、インド国内だけではなく、スズキのように、インドからグローバルサウス諸国などの外に輸出していく絶好の機会だと思います。
羽生田:
端的に言えば、アライアンス競争に乗り遅れるな、ということになります。ASEAN・インド市場では今後、企業の入退場が盛んになるとみています。例えば、顧客がいなくなる、採算が悪化したため工場を売却するなど、退場も、反対に入場も増えるでしょう。その際に、中国企業に負けずに地場企業に対する目利き力を発揮することが重要です。昔からいる企業の入退場、そして新しいスタートアップ企業の入退場をうまく取り込むチャンスですが、このままでは乗り遅れてしまうかもしれません。政府による情報共有や与信などでの支援も必要かもしれません。
市場の重心が東から西に移っているインド太平洋
篠田教授:
日本企業がインド太平洋地域においてどこを目指すべきかという話ですが、重心が東から西に移ってきているという状況かと思います。現在、東に当たる中国には、約1万3000社の日本企業が進出し、3万の拠点があります。ただ、今後はASEANやインドで人口やGDPの伸びが大きくなるので、中長期的には、アフリカ市場も含めて、日本企業は西を目指していくべきではないかと思います。そのためにできる政府による支援は、まずはFTAの拡大でしょう。先ほど既存のFTAの質を高めていくという話をしましたが、未締結の諸国に広げていくことも重要です。既に交渉が行われているバングラデシュやGCC(湾岸協力理事会:サウジアラビア等湾岸6カ国で構成)、8月のTICAD(アフリカ開発会議)時にはアフリカ諸国とのFTAの検討も始まりました。
分野としては、サプライチェーンの強靱化やDX(デジタル・トランスフォーメーション)、GX(グリーン・トランスフォーメーション)が、日本政府として企業を支援する重点分野になっていると思います。相手国の社会課題の解決につながるように、製造業だけでなく、サービスやデジタル産業も含めて、日本として支援していくということです。AZECやADX(アジア・デジタル・トランスフォーメーション)はその例です。
現在、ASEANへの投資では中国が日本を上回っています。1980年代に日本企業がASEANに進出してサプライチェーンを拡大・強化したのと同じようなことが、今後中国のASEAN進出によって起きるのではないかとの指摘があります。その時に、日本企業は中国企業とどう向き合うのか。ASEANのような第三国で対抗することもあれば協力もする、インドなどの中国のプレゼンスが比較的低い国を目指すというのもあるかと思います。多様な戦略の検討が必要になると思います。
モデレーター:
3回の対談に続き、座談会でも大変有益なお話を伺いました。どうもありがとうございました。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
代表取締役 CEO
羽生田 慶介
関連レポート・コラム
ASEANと中国ではどちらからの輸出が得か、関税地獄の中でFTAをどう活用すべきか…トランプ2.0の負けない貿易戦略(2025年9月 JBpress掲載)
ブロック化する世界の中で重要度が増すCPTPP、瓦解する自由貿易体制を守り抜くために必要なASEANとの連携深化(2025年10月 JBpress掲載)
インド太平洋地域の新たな通商枠組みにおけるデジタル分野のルール形成(2023年2月 月刊アイソス掲載)
続・パワーアップしたタリフマン2.0(2025年7月 JMF経済ニュースレター掲載)
トランプ2.0で経済安全保障はどう変わるか? (2024年11月 JBpress掲載)
2024年地政学・経済安全保障 クリティカル・トレンド(2024年1月 JBpress掲載)
「地政学リスク」とは|事業環境の変化に備える
「経済安全保障」とは①|日本の取り組みと企業に求められる対応
「経済安全保障」とは②|主要国(米国・EU・中国)の取り組み
IPEF(インド太平洋経済枠組み)とは|交渉のポイント
グローバルサウスとは |国際秩序を揺さぶる新勢力と日本企業の戦略
関連サービス