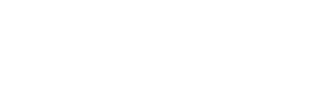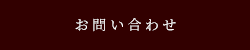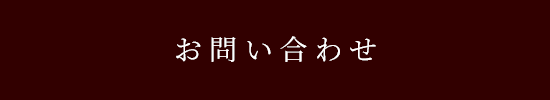「次女が生まれてきた意味を作りたくて」、子どもの入院に付き添う親を支援しようと思った理由(2025年6月 JBpress掲載)
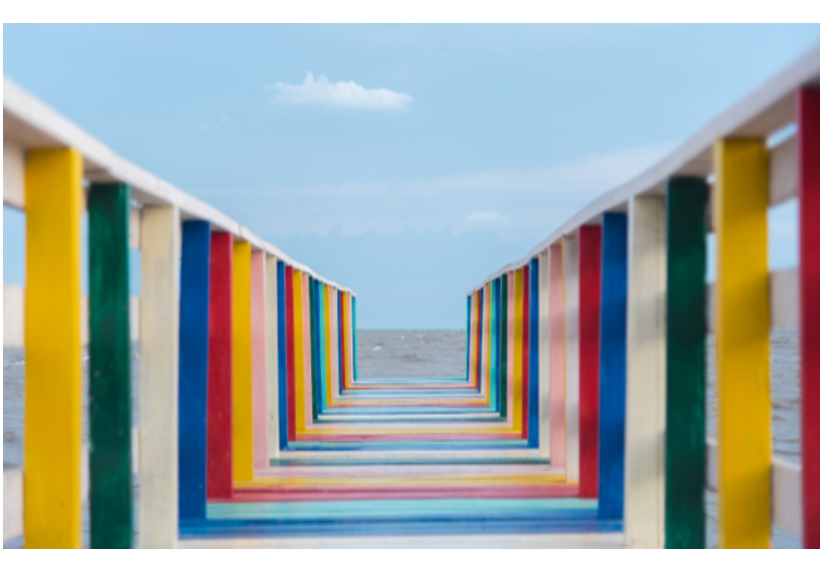
※2025年6月16日付のJBpressの記事を一部変更して掲載しています。
子どもの入院は、ある日突然やってくる――。長女と次女の入院を経験し、過酷な「付き添い入院」の現実に直面した光原ゆき氏は、入院中の子どもとその家族を支える仕組みをつくるため、認定NPO法人キープ・スマイリング(以下、キープ・スマイリング)を設立しました。今回は、弊社のJBpress連載シリーズ「見過ごされた社会課題に光を」の第2回目として、キープ・スマイリング理事長の光原氏に、付き添い入院の実態とその背景にある社会的課題について、弊社シニアマネジャーの石井 麻梨が伺いました。
生後5日で8時間の大手術に
──光原さんはもともと、リクルートでお仕事をされていたそうですね。
はい。子どもを産む前は、終電に間に合えばまだ良い、という働き方をしていました。その中で、一般の方を対象とした医療系のウェブメディアの立ち上げに関わったことがあり、日本の医療制度や課題については、ある程度の知識はありました。
そんな中、35歳で長女を出産しましたが、産休に入るギリギリまで働いていて、「出産後もすぐに復帰しよう」と思っていました。仕事を休むのはほんの数カ月。そう考えていたのです。
──ところが、そうはならなかった。
出産してすぐ、赤ちゃんの様子がおかしいと言われ、気づけば「大学病院に搬送します」と、娘だけ救急車で搬送されてしまったんです。その後、いくつもの検査を経て、何万人にひとりという難しい病気が見つかりました。
「すぐに手術します!」と言われ、生後5日で8時間の大手術に……。もう頭が真っ白でした。すぐに仕事に復職するのは難しいだろうなと、頭をよぎりました。
その後は集中治療室に入り、しばらくして個室に移ることができたのですが、看護師さんに「お母さん、一緒に泊まれますか」と聞かれて。ああ、親が付き添って泊まるものなんだと初めて知ったのです。そういうことも、それが「当たり前」だということも、まったく知りませんでした。
──初めての付き添い入院ですね。
初めてだったので、看護師さんに「お母さん、これお願いします」と言われれば、「はい」と言われるがままに動いていました。
たとえばそのとき、娘は鼻からチューブでミルクを入れていて。ミルクを温めて、点滴用の器に移し、管がちゃんと通っているかを聴診器で確認して、流れるスピードを調整しました。そういう一連のケアを「親がやるもの」として教わりながら、とにかく「自分がやらなきゃ」と必死にやっていました。
2人目の妊娠で告げられたまさかの現実
──かなり忙しい日々だったのですね。
本当にそうでした。朝起きたら離乳食やミルクの時間があり、おむつ替え、検査の付き添い、採血室への移動……と、とても忙しく過ごしていました。その合間に、自分の食事やトイレ、それからシャワーなど、なんとか時間を見つけてこなしました。
──シャワーがあるんですね。
病院によりますが、私が付き添った病院では、共用のシャワールームが小児病棟に2つくらいありました。シャワー室前のボードに浴びたい時間を記入する方式で、毎朝早い者勝ちで記載していました。
ただ、その時間にちょうど検査が重なってしまったり、子どもが泣いて部屋を離れられなかったりすると、入れないこともありました。保育士さんがいた病院では、シャワーの間子どもの面倒を見てもらえて本当に助かりましたが、そうではない病院の場合は、毎日浴びるのが難しかったです。
──食事はどうしていたのでしょうか?
前編で少しお話しした通り、たいていの病院では、親の食事は自分で用意しなければなりません。ある私立の大学病院では、ありがたいことに病院食を親にも有料で提供してもらえました。ただ、あとで他の病院を経験する中で、常食と呼ばれる病院食が出る病院はとても珍しいのだと知りました。
──仕事のほうはどうなったのでしょうか。
すぐに復職はできなかったので、1年間の育休をとりました。その後、長女が保育園に通えるようになってから復職し、入退院を繰り返しながら仕事と育児を両立していた感じでした。
そんなときに2人目を授かりました。39歳での妊娠ということもあり、高齢出産のリスクも踏まえて、長女がお世話になった大学病院で妊婦健診を受けることにしました。そこで、健診中に「あれ?」という異変が見つかり、長女よりさらに難しい病気であることがわかったんです。
医師からは、「出産後すぐに手術が必要です。手術をしても普通の生活は難しいかもしれません」と言われました。またあの入院生活が始まるのかという覚悟と、きっと退院後の子育てと仕事の両立はもう難しいだろう。これからは子どもに寄り添って生きていこうと気持ちを決めました。
夜中の病棟で目の当たりにした看護師の実情
──そしてまた入院の付き添いの日々がはじまったのですね。
それが、私は泊まるものだと思っていたのですが、その病院は「原則、面会のみです」といわれました。しかも病院は自宅から遠く、私も産後まもない体でしたので、毎日面会に通うのはとても大変そうだな……と感じました。
こういった難しい病気のケースでは、近くの病院に入院できず、専門性の高い遠方の病院に入院することが多くなります。そのため、病院の近くにある、家族が滞在するための施設「ファミリーハウス」に宿泊することになりました。
1泊1000円くらいで宿泊できる施設で、私も地域のNPOが運営しているファミリーハウスに宿泊しました。面会は、朝10時から夜10時までと決まっていたので、毎日その時間に合わせて病院へ行き、就寝を見届けてから施設に帰るという生活でした。
でも、ある朝面会に行くと、娘の顔の横にタオルが積まれていて、その上に哺乳瓶が置かれていました。その光景には、正直ショックを受けました。
万が一、誤嚥になったらどうしようと心配でしたし、保育園で同じことを保育士がやっていたらきっと大問題になるのではと思いました。でも、病院では手が足りないから普通のことになっている。だったら、私が泊まってサポートしたいと強く思いました。
──看護師さんも、どうにもならない人手不足の中で必死なんですね。
そうなんです。その後、個室なら泊まれることがわかり、個室に移って付き添い入院を始めました。夜中にふと気になって、少し病棟の中を歩いてみると、ひとりの看護師さんが8人くらいの新生児のケアをしていたんです。こっちの赤ちゃんにミルクをあげたら、タオルの上に哺乳瓶を置いて寝かせて、また別の赤ちゃんへ……そんなふうに一人で対応されていて、本当に大変そうでした。
私は泊まり込んでいたので、ミルクはもちろん、排泄の量を測ってお知らせしたり、これまでの病院でしていたことを手伝っていたりしたら、「本来は私たちの仕事なのにお母さんにさせてしまって申し訳ありません」と謝られてしまいました。他の病院では当たり前のようにお母さんがみんなやっていたことなのに……。実は、病院によって環境に大きな差があるということを現場の方自身も知らないままなんだと気づきました。
──いろいろな病院を見てきた光原さんだからこそ、見えてきた問題点です。
そうかもしれません。けれど、その後、次女の容体が急変してしまい、1歳を迎える前に旅立ってしまいました。もう私は泣くことしかできなくて、どうしていいか分からずに絶望の中にいました。「私に何かできたことはなかったのか」「この子が生まれた意味はあったのか」――。答えの出ない問いが、頭の中でぐるぐると渦を巻いていました。
短い人生だったけれど、彼女と出会えたから私が知ったことで、何かをよりよく変えることができたら、それはきっと彼女の生まれた意味になる。そう思うことでようやく顔を上げることができました。
そのときに、ふと思い出したのが、病院で過ごした日々のことでした。そういえば、なんで病院ごとにルールが違うのか。ある病院では病院食をベッドサイドまで持ってきてもらえたのに、どうして食べられない病院もあったのか、とシンプルに不思議だったことを思い出したのです。
たとえば、部屋ごとにシャワールームがある病院はすごく楽だったな、保育士さんがいてくれる病院もとても助かったな──など、付き添い入院を複数の病院で経験した自分だからこそ、「おかしいな」「こっちの方がいいな」って気づくことができたんじゃないか。そう思うようになりました。
「入院付き添い中も、美味しいものを食べてほしい」配付数が累計1万人を超えた「付き添い生活応援パック」
──そこが、キープ・ママ・スマイリング(現キープ・スマイリング)を立ち上げる原動力になったのですね。
はい。いくつかの病院で付き添い入院をしたからこそ見えた課題はありましたし、当事者の視点があることは、自分の大きな強みだと思いました。次女が亡くなった2014年の11月、NPO法人を設立するに至ったのです。少しでもこの過酷な付き添い環境の改善に貢献できたら、次女が生まれてきた意味にもきっとつながる──。そんな気持ちを込めてのスタートでした。
──リクルートのお仕事とはどのように両立させていたのでしょうか。
「毎月何か必ず活動しよう」と決めて、まずは料理が得意な友人たちと一緒に、ドナルド・マクドナルド・ハウス[1]のキッチンで調理し、滞在中のご家族に届けるという活動から始めました。
そしてコロナ禍に、「付き添い生活応援パック」無償配付事業が始まりました。現在では累計で1万人を超えるご家族に届けることができています。この5年ほどで企業からのご支援も増え、多くのお子さんとご家族に笑顔と安心を届けることができたと思っています。
企業との連携は大きな鍵となりましたが、社会貢献といっても、企業にご支援いただくのは簡単ではありません。ですが、自分が企業で働いていた経験があるので、企業の目線も意識してご提案できているのかもしれません。
──今後はどのような活動をしたいと思っていらっしゃいますか?
活動の軸は何も変わっていません。ただ、昨年、国が診療報酬を改定したことを受け、付き添い環境改善のバトンは、国から病院へと託されました。それを受け、私たちも小児病棟への直接支援を少しずつ始めています。目指しているのは、「入院中の子どもと付き添う親、小児病棟で働くスタッフも、みんなが笑顔でいられる環境」をつくることです。
設立10周年という節目に、団体のビジョン・ミッションをあらためて再定義しました。「これまでの延長」ではない、次のフェーズの付き添い環境改善を私たちの使命とし、ビジョンには”Keep Smiling!”――子どもを真ん中に、みんなが笑顔でいられる社会を掲げました。
団体名も(キープ・ママ・スマイリングから)「認定NPO法人キープ・スマイリング」へと変更し、「ひとりの付き添いを、みんなの寄り添いに。」というキャッチフレーズも紡ぎ出しました。
私たちが目指す“子ども真ん中のチーム”には、「企業」も欠かせない存在です。実際、企業の中にも、子どもの入院を経験した方は決して少なくありません。ただ、年に一人いるかいないかくらいの頻度だと、制度として整備されにくいのが現状です。
だからこそ、その「一人」をきちんとサポートできる体制を、企業の中にも整えてほしい。たとえば、「子どもの付き添い休暇」や離職を防ぐための柔軟な働き方のしくみなど、できることはまだたくさんあります。
今は、企業の中でも、社会貢献やプロボノへの関心が高まっている時代です。企業ができることと、社会が求める支援の場とをうまくマッチングさせること。それも、私たちの大事な役割だと感じています。少しずつでも、誰かが動けば社会はきっともっとよくなる。私はそう信じています。
[1] 公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンが運営する重い病気と闘う子どもと家族のための滞在施設
株式会社オウルズコンサルティンググループ
シニアマネジャー
石井 麻梨
関連サービス