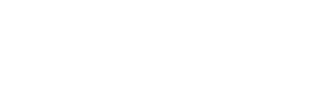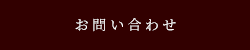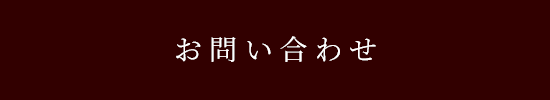“付き添い入院”の現実、子どもが入院で親が直面する過酷な日常(2025年6月 JBpress掲載)

※2025年6月16日付のJBpressの記事を一部変更して掲載しています。
子どもの入院は、ある日突然やってくる――。長女と次女の入院を経験し、過酷な「付き添い入院」の現実に直面した光原ゆき氏は、入院中の子どもとその家族を支える仕組みをつくるため、認定NPO法人キープ・スマイリング(以下、キープ・スマイリング)を設立しました。今回は、弊社のJBpress連載シリーズ「見過ごされた社会課題に光を」の第1回目として、キープ・スマイリング理事長の光原氏に、付き添い入院の実態とその背景にある社会的課題について、弊社シニアマネジャーの石井 麻梨が伺いました。
子どもが入院したら親が面倒を見るのが当たり前?
──まず、子どもの入院について詳しく聞かせてください。お子さんの入院が決まると、親はどのような生活になるのでしょうか。
病院によって細かなルールはさまざまですが、大きく分けると、親が「付き添う(院内に泊まる)」か「付き添わない(面会)」かの2択です。どちらかを選べないケースが多く、家族の事情にかかわらず、付き添いが半ば強制されたり、付き添いたくても付き添えなかったりします。
付き添う場合は、子どものベッドで小さくなって眠るか、病室に簡易ベッドを置き、そこで寝泊まりします。付き添わないときは、親は面会時間にだけ病室に入ることができます。
付き添いたくてもきょうだいがいたり、ひとり親だったり、仕事があったりして、実際に付き添えるかどうかは別の問題です。また、付き添えない病院に入院した場合は面会に通うことになりますが、家が遠方だと移動も交通費も大変になりますね。
──光原さんはお子さんの入院のとき、付き添っていらっしゃったんですよね。
最初に長女が入院した病院は、ほぼ付き添うことが前提という雰囲気でしたので、私自身は「子どもが小さいと親も一緒に泊まり込むものなんだ」と思い、付き添いました。ですが、その後、複数の病院に入院し、病院によってさまざまなルールがあることを知りました。私自身としては付き添いを希望し、可能なところはすべて付き添っていました。
NPO設立後、リアルな声をもっと聞きたいと思い、子どもが入院中の親の声を調査しましたが、付き添うにしても付き添わないにしても、親はかなり過酷な状況に置かれているということが分かりました。
付き添いの大変さは、院内でずっと子どもの面倒を見ているにもかかわらず、暮らす環境が整っておらず、心身に大きな負担がかかることです。親は「子どもが一番頑張っているんだから」と自分のケアにまで手がまわらない。のちに行った調査では、約半数が体調を崩したことがあるとわかりました。
また、毎日病院で寝泊まりしていると、だんだんと病院の状況も見えてきます。医師や看護師がいかに忙しく声もかけづらい状況かということ、そしてどなたも子どもに一生懸命に向き合い、力を尽くしてくださっているということは明らかでした。
だからできる限り、自分の子どものことは自分でやろうとしました。おむつを替えたり離乳食を食べさせたり、沐浴したりという家庭でも行うことはもちろん、服薬、検査に連れていったり、細かな変化を観察・記録して医師や看護師に伝えたり、とにかくやることが多くて日中は忙しかったですね。
食べられない、眠れない、目が離せない。精神的に病んでしまう親
──目まぐるしい忙しさですね……。
その合間に、自分の食事やトイレ、シャワーも済ませなければなりません。親の食事を有料で提供してくれる病院もありますが、それはごくわずかです。多くの場合、親は自分で食事を用意しなければなりません。子どもが寝た隙に走って院内のコンビニで何か買うくらいがやっとです。
ただ、入院も長期間になってくると、毎日コンビニはつらいし、そもそも落ち着いて食べられません。付き添うお母さんから、「入院してこの1年、外に出たことが一度もないんです」と話されたときは言葉を失いました。
──ゆっくり眠ることもできないですよね。
そうですね。簡易ベッドは幅が60cmくらいしかなく、1時間おきに看護師さんの見回りがあるため、気配で目が覚めてしまいます。さらに、病室内ではピコン、ピコンと医療機器の音も常に鳴り、そこに授乳やミルクの時間がある。
私も赤ちゃん用の小さなベッドに身を縮めて添い寝しながら、おっぱいをあげたりしていましたが、そんな状況が続けば、腰痛も不眠も慢性化します。「食べられない」「眠れない」「目が離せない」。私たちの調査でも、この3つが付き添いの親の“困りごと”のワースト3として上位にあがっています。
──お金の面ではどうでしょうか。子どもの入院については、医療費控除がありますが……。
日本では、子どもの医療費が多くの場合、公的支援によって無料になります。これは、本当にありがたい制度だと思います。ただ、いざ入院となると、親自身のごはん代、レンタルベッド代、冷蔵庫やテレビや洗濯代など、細かな出費が積み重なります。また、泊まり込んで付き添いができないご家庭では、毎日の面会に通う交通費が大きな負担となります。
そして、付き添いでも面会でも、仕事との両立は非常に困難です。実際に仕事ができなくなり、生活保護を申請した方もいらっしゃいます。子どもの病状への不安に加え、経済的な負担や将来への不安も重なり、精神的に追い詰められる方も少なくありません。
──家に残った他のご家族も大変ですよね。
そうなんです。たとえばお母さんが病院につきっきりになると、家に残るきょうだいはお母さんになかなか会えません。その間に保育園や学校の行事があっても出られない。子どもへの精神的な負担はもちろん、親自身も「きょうだいの面倒を見てあげられない」ということに罪悪感を抱えることも少なくありません。 子どもがひとり入院するという出来事は、家族みんなに、物理的にも精神的にも大きな負担をもたらすのです。
人手が足りない医療現場で起きていること
──そこまで親にいろいろ強いられてしまうのは、なぜなのでしょうか。
背景には、小児病棟の深刻な人手不足があると思います。たとえば、保育園では保育士1人が担当する子どもの人数が、年齢に応じて明確に定められています。一方で、病院では、看護師の配置基準は患者の年齢に関係なく、病院の規模や機能によって定められています。たとえば、大学病院のような大きな医療機関なら、日中は「7対1」、夜間は「10対1」という基準が一般的です。これは、看護師1人が7人(または10人)の患者を担当するという意味ですが、これは大人の病棟でも子どもの病棟でもこの基準はほとんど変わりません。
しかし、ミルクをあげたり離乳食をあげたり、入院中の赤ちゃんをひとりで7人も10人も担当するのはどう考えても不可能です。つまり、小児病棟に必要な「手間の多さ」が考慮されていないのです。
その結果、現場では親が「看護師のサポーター」のように動かざるをえません。そのため、多くの病院で、特に子どもが未就学児の場合は、親の付き添いを要請することになります。「付き添えないなら手術はできません」「別の病院を探してください」と言われることすらあります。
では、なぜ人員を増やせないのか──。たとえ看護師を増やして人件費がかかったとしても、それに見合う病院の収入(診療報酬)が病院に入ってくるわけではないからです。
そもそも、一般的に小児の入院治療における診療報酬は、他の診療科と比較しても低く抑えられている傾向があります。つまり、経営的に見れば、収入が限られている小児科に十分な人員を配置するのは難しいということです。このような構造的な問題の中で、病院はどうしても親の力を頼りにせざるを得ない。これが、今の日本の小児入院医療の現状なのです。
──面会が前提の病院では、どんな対応をしているのでしょうか。
原則として「付き添い不可」で、面会のみが前提となっている病院についても、前述の看護師の配置基準に大きな違いはありません。親が病室にいない分、現場の看護師にはより多くの負担がかかっているのが現状だと思います。たとえば、県立の子ども病院などでは、県からの補助金で看護師の数を手厚くしているところもありますが、それでも人手は十分とは言えず、病院経営も厳しいと聞いています。また、面会時には、親は子どもの身の回りのケアやお世話を担当することも多く、実質的には「部分的な付き添い」のような状態になることもあります。
とはいえ、親が家に戻って生活できるというのは、付き添いとは異なる側面で良い点もあります。遠方からの面会は体力的にも大変ですが、家ではきょうだいの世話もでき、足を伸ばしてお風呂に入ったり、寝返りを打って眠ったりと、身体を休めることができます。もちろん、それは「病院に子どもを安心して任せられる」という信頼があってこそ成り立つものです。
──親の多くはその現状に不満を持っているのでしょうか。
最近はSNSで発信する親も増えてきましたが、当事者自身も、「個人的な非常事態」「これが当たり前で、仕方がない」と思って、声をあげる人がほとんどいなかったのだと思います。
病院同士で情報を共有する機会もなく、子どもに付き添う家族の置かれている過酷な状況は、医療制度の「隙間」に落ちたまま長い間見過ごされてきました。日本の小児医療は世界に誇れるほどの高い水準を持っていると心から思います。でも、その素晴らしさの陰で、社会的に見過ごされてきた問題が、今も確かに存在しているのです。
「入院付き添い中も、美味しいものを食べてほしい」
──現在はどのような活動をしているのでしょうか。
私が子どもの入院を経験して一番つらかったのは「食事」でした。食べる時間も買いに行く時間もない。倒れないための栄養をコンビニで買うという感じで、温かいスープを飲んでほっとしたり、魚や野菜を味わったりする時間はほぼありませんでした。そんな中で私がまず考えたのは、美味しいごはんでかつての自分のように付き添い中の親を応援しよう、ということでした。団体設立後、ご縁をいただいたドナルド・マクドナルド・ハウスせたがやで食事を作り、遠方から子どもの入院・治療のためにハウスに滞在するご家族を美味しいご飯で応援する活動からスタートしました。
また、小児病棟で付き添うご家族にも手作りのご飯を届けられたら、と病院に相談したこともありましたが、衛生面の懸念もあり、現実的ではありませんでした。そんなとき、缶詰を小ロットで製造できる会社の社長と出会ったのです。
──缶詰だと、いつでも好きなときに食べられて、衛生的にも心配がなさそうです。
そうなんです。『No Code』の米澤文雄シェフのご協力も得て、全国の小児病棟で付き添うご家族に届けるための4000缶のオリジナル缶詰が完成しました。ただ、「やっと全国のご家族に食の支援を届けられる!」と喜んだ矢先に、新型コロナの感染拡大が始まってしまったのです……。一気に病院のルールが厳格化され、面会が禁止となり、付き添いの親も一度病院に入ったら原則外に出られない状況になりました。
病棟内では、他の入院患者やその親と話すこともできなくなり、おもちゃがあるプレイルームや待合室などの共有スペースも閉鎖。親たちは誰とも言葉を交わせないまま、閉ざされた空間で付き添い生活を送ることになりました。院内のコンビニに買い物に行くにも時間や回数に制限がある病院もあり、物理的にも、精神的にも、想像以上に過酷な付き添い環境となりました。
──そんなときに、キープ・スマイリングの支援に助けられたという声も聞いています。
そこで私たちは、長期間泊まり込みで付き添っているご家族に、「今、本当に必要なものを届けよう」と考えました。缶詰に加え、さまざまな企業から商品のご提供を受け、食品・衛生用品・生活用品を詰め合わせ、「付き添い生活応援パック」という一箱にして病室まで送るという支援をはじめたのです。(応募時点から10日以上お子さんと一緒に小児病棟に泊まり込む保護者が対象)
子どもの入院は、「今すぐ入院してください」と突然告げられる、緊急入院が多いです。必要なものを考える余裕も、荷物を用意する時間もなく、自分のものを持ち込んでいない方が多いのです。だからこそ、少しでもお役に立てればと、病棟でのチラシの掲示や、長期泊まり込みになる家族へのご紹介を、看護師長さんやスタッフの皆さまにお願いしています。ありがたいことに、広報にご協力くださる病院は年々増えており、「病棟でチラシを見ました」「看護師さんに教えてもらいました」という声も多く寄せられるようになりました。実際、応募者の半数は、院内でこの支援を初めて知ってくださった方々です。
子どもを真ん中にして制度を変えていく
──一方で、国に対する働きかけも行なっているそうですね。
はい。もちろんご家族への支援は最も大切ですが、それだけでは状況そのものを変えることはできません。制度や社会の仕組みが変わらない限り、同じ困難が続くからです。
付き添い環境改善という観点において病院にできることはもちろんありますが、問題の本質は医療制度そのものにある。「小児の入院付き添い」の本質的な課題と現状を国に理解して改善してもらいたい、そう考えました。
実態と課題を定量的に明らかにする必要があると考え、調査チームを立ち上げ、付き添い家族の実態調査(「入院中の子どもに付き添う家族の生活実態調査」(キープ・スマイリング))をはじめました。
当初は「1000人ほど回答が集まれば」と思っていたのですが、結果的に集まったデータは3643件にものぼりました。付き添い生活応援パックを受け取ったご家族からの協力が大きかったですね。これはすべて「過去5年以内に子どもの入院を経験した方」からの回答であり、現実の声に裏打ちされた、非常に信頼性の高いデータとなりました。
──こども家庭庁ができたというタイミングも追い風となりましたね。
はい。調査データと要望書を厚生労働省・こども家庭庁にお持ちした際には、多くのメディアが取り上げてくださいました。厚生労働省での記者会見の場もとても温かく、非常に前向きな反応をいただきました。
お伝えした要望は3つ。「希望して付き添う家族の環境改善」「医療機関側への付き添いの実態調査の実施と改善策の検討」「付き添い環境改善に向けた検討会の開催」です。
私たちの調査によって数値として明らかになったのは、前述した「食事・睡眠・(子どもの)見守り」の3大困りごと。加えて経済的な負担やきょうだい児の課題です。私たちとしては、環境改善の一歩としてまず「食事・睡眠・見守り」からなんとかしてほしいとお願いしました。
要望書をお届けした翌日、こども家庭庁の大臣が「国としてこの問題に取り組みます」と表明してくださいました。その後、日本小児科学会、有識者、当事者、弁護士などによる検討会が立ち上がり、全国の病院の付き添い環境の実態調査も行われました。
──制度を変えていくということは、やはり病院側の体制にも関わる問題ということでしょうか。
その通りです。ただ、私たちが一貫して大切にしているのは、「病院vs親」という対立構造を作らないことです。というのも、病院や医療スタッフは、限られた条件の中でできる限りのことをしてくださっています。問題は、病院単体で解決できるものではなく、医療制度全体の仕組みの中にあると私たちは考えています。
親の大変さが一方的に伝わると、「それなら付き添いなんてなくせばいい」という極端な意見に繋がってしまうことがあります。しかし、それは違います。そもそも、親と医療者は役割が違います。子どもにとって、不安なときに親がそばにいてくれることはとても大切なことであり、それは「子どもの権利」です。
だからこそ、付き添いを選んだご家族が、心身をすり減らすことなく、安心して人間らしい生活を送れる環境が必要なのです。同時に、付き添わない選択をした場合であっても、安心して子どもを病院に任せられる体制が整っていることが必要なのです。
病院側にも事情があります。だからこそ、すべての関係者(ステークホルダー)──医療者、行政、当事者、支援団体などが顔を合わせ、子どもたちを真ん中に、子どもにとっての最善の利益のために何ができるかを一緒に考える。まずはその場を持ち、そうした「チーム」としての姿勢が、今後ますます必要になっていくと感じています。
──その結果として、小児入院における令和6年度の診療報酬改定において、キープ・スマイリングの要望が反映されることになったのですね。
はい。「家族が希望して付き添う場合は、食事と睡眠環境への配慮を行うこと」が小児入院医療管理料の要件として明記されました。また、令和7年度のこども家庭庁の予算で、付き添い環境の改善に向けた予算も新たに組まれることになりました。
このように制度の中に家族の存在や付き添いの現実が組み込まれたことは、本当に大きな前進です。ただ、これが本当の意味で付き添い環境改善につながるかどうかは、これからの運用次第です。
私たちは支援団体として、付き添い当事者や医療者の代弁者として声を集め、国や行政、学会などへと必要な働きかけを行なっていくつもりです。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
シニアマネジャー
石井 麻梨
関連サービス