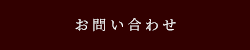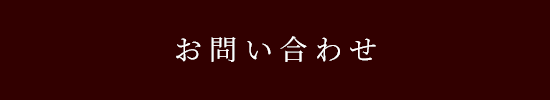2022年、政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、日本企業でも人権尊重の取り組みが進んでいる。最近では、自社内での人権侵害リスクに対応するだけでなく、原材料等の調達元などサプライチェーンの「川上」にあたる取引先にも人権尊重を求める企業が増えている。一方、企業の製品が販売先でウイグル人の弾圧やロシアによるウクライナへの軍事侵攻等に用いられているとして、販売元の企業が批判されるケースも出てきている。製品・サービスの販売先、つまりサプライチェーンの「川下」で懸念されるこうした人権リスクにどう対応すべきか、頭を悩ませるビジネスパーソンも多いのではないか。本稿では「販売先での人権リスク」を巡る動向、国内外のルールの考え方、企業に求められる具体的なアクションについて解説する。

※2023年10月31日付のJBpressの記事を一部変更して掲載しています。
置き去りにされる「川下」の人権リスク
近年、企業に「ビジネスにおける人権尊重」への取り組みを求める動きが加速している。2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、国連指導原則)はあらゆる企業に「人権を尊重する責任」が適用されることを初めて明言し、その後欧米を中心に人権デュー・ディリジェンス(事業を通じて及ぼしうる人権への悪影響を特定し、防止・軽減するための取り組み)を義務付ける法律の整備が次々と進んだ。遅れをとっていると言われていた日本政府も2022年には「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、いよいよ本腰を入れ始めた。
日本でも人権尊重の取り組みに力を入れる企業が増えている。特に最近では、自社内での人権リスクに対応するだけでなく、原材料等を調達しているサプライヤー、言い換えればサプライチェーンの「川上」にあたる取引先に対しても人権尊重を求める動きが活発化している。JETROの調査によると、大企業の51.4%が、調達元の企業にも自社が定めた「人権方針」への準拠を求めているという。人権の尊重を含めたサプライヤーへの要求事項をまとめ、「調達ガイドライン」等の形でルール化している企業も多く見られる。
一方、製品・サービスの販売先である「川下」に相当する部分についてはどうか。調達先での人権リスクと比べ、これまで「売った後」の人権リスクはあまり注目されてこなかった。もっともBtoC企業の場合は消費者からの意見や訴訟に直面することもあり、自社製品が販売された後に人々の安全や健康等に悪影響を及ぼしていないかを意識する局面が多少なりとも存在する。他方、BtoB企業の場合はこうしたケースは少なく、「川下」の人権リスクに関する意識は特に希薄であったと言わざるを得ないだろう。
「売った後のことは知りません」では済まされない時代に
しかしいまや企業や政府を顧客とするビジネスであっても、販売先で起きることについて「売った後のことは知りません」では済まされない時代になっている。例えば2022年2月に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻では、ロシア軍のドローンに複数の日本企業のカメラやエンジンが活用されている可能性があると報じられた。また、2023年に入ってからも、国連の元高官らが、ミャンマー軍が自国民に対して使用する武器が、日本を含む外国企業の機器を用いて製造されていると指摘している。「自社の製品が悪用され、知らないうちに人権侵害を“後押し”してしまった」という事態が充分に起こりうるのだ。
自社の技術が紛争や弾圧に用いられるケースに加え、製品・サービスの提供が人権侵害を行う政府や企業に金銭的な利益等をもたらすケースも批判の対象となる。2018年には、ミャンマーのヒスイ鉱山の採掘に用いられる建設機械が小松製作所、キャタピラー、ボルボ建設機械等の生産したものだとNGOが指摘した。NGOは、ヒスイ鉱山がミャンマー国軍や旧軍事政権の紛争の資金源になっており、企業が販売先での実態を把握するために具体的なアクションをとらないことは「深刻な緊急事態」だとしている。 もっとも、経済安全保障の世界では、これまでも製品・サービスの販売先である「川下」を見据えて対応することは当然とされてきた。地域紛争防止の観点から通常兵器や関連汎用品・技術の輸出管理を目指して1995年に発足した「ワッセナー・アレンジメント」等の国際的な枠組みがその代表的な例だ。本年3月には、軍事用でも非軍事用でも利用可能ないわゆる「デュアルユース製品」による人権侵害の防止を目指す「輸出管理と人権イニシアチブ」に関する行動規範を米国が新たに主導して策定し、「人権」というキーワードが明確に打ち出された。輸出管理に関する国内外のルールの動向や実施状況の確認、新たな技術がもたらし得る脅威やリスクに関する情報や輸出管理のベストプラクティスの共有等に多国間で取り組む枠組みであり、日本を含む25か国が参加している。こうした国際社会の動きもあり、近年の軍事侵攻や強制労働等の人権問題に企業の製品・サービスが「販売先を通じて間接的に加担している」ケースに対しては、ますます厳しい目が向けられ始めている。
国際ルールが示す「サプライチェーン」と「バリューチェーン」の違い
「そうは言っても、販売先で製品が悪用されるリスクまではコントロールしきれない」と疑問を抱く向きもあるだろう。近年、人権デュー・ディリジェンスに関する国際ルール形成が加速しているが、その全ての基盤となっている国連指導原則では「販売先における人権リスク」をどう位置付けているのか見てみよう。
国連指導原則では、企業は事業を通じて及ぼしうる人権への悪影響を特定し、防止・軽減する「人権デュー・ディリジェンス」を実施するべきとされている。その際に見るべき「人権への悪影響」は、原材料等の調達元である「川上」のサプライチェーンで発生するものだけでなく、製品・サービスの販売先である「川下」で発生するものまで含む。つまり、企業の人権尊重の責任範囲はやはり「川上」から「川下」までバリューチェーン全体に及ぶのだ。2023年に改訂されたOECDの「多国籍企業行動指針」でもこの点が改めて明記されたほか、日本政府のガイドラインも同様の立場をとっている。 なお、EU全域への適用を前提に現在策定されている「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令」案では、まさにこの「川下」の人権リスクの扱いが一つの争点となっている。産業界や欧州理事会の各国代表等からは「人権デュー・ディリジェンスを義務付ける範囲を『川上』のサプライチェーンに限定すべき」との意見が出されたが、2023年6月1日に欧州議会が示した案では「川下」も含むとされている。EUのルールでも指導原則と同様、バリューチェーン全体を通じた対応が求められる可能性が高く、やはり企業は販売先での人権リスクに取り組む必要があるのだ。
顧客に対して人権の尊重を求める動きも
では、販売先を通じた紛争や弾圧等への加担のリスクに対応するため、企業は具体的に何をすべきなのか。 通常、販売先との力関係はサプライヤーとは大きく異なる面があり、サプライヤーを管理するのと全く同じ方法で対応することは難しいだろう。しかし、国連指導原則等に基づく基本的な考え方や押さえるべきポイントは変わらない。
まずは自社の策定する人権方針等の中で、「川下」の人権リスクについても考慮する旨を明示するのが望ましい。例えばドイツの大手自動車部品メーカーのボッシュは、人権の尊重や児童労働・強制労働の禁止等の要求事項を定めた「ビジネスパートナー向け行動規範」を策定している。「サプライヤー」ではなく「ビジネスパートナー」という用語を用いた意図として、同社はサステナビリティレポートの中で「社会的責任に関する方針やプロセスは、販売先を含むすべてのビジネスパートナーに適用される」と説明している。このように「ビジネスパートナー」「取引先」「バリューチェーン」等の表現を用いることで、自社の方針やルールの適用対象に販売先も含む形にするのは現実的な方法の一つだろう。
また、事業を通じて及ぼしうる人権への悪影響を特定する際には、自社や原材料等を調達しているサプライヤーだけでなく、「川下」の販売先も視野に入れるべきだ。もし販売先で紛争や弾圧等の深刻な人権侵害への加担のリスクがある場合は、それを防止・軽減するための措置を優先的に講じる必要がある。こうした取り組みの一例として、スウェーデンの大手通信機器メーカーのエリクソンは、自社製品の販売時に人権の観点で問題がないかチェックするプロセスを取り入れている。具体的には、自社製品・サービスが個人情報に関連する技術を含むか、どのような目的で使用されるか、顧客の所有形態はどのようなものか、販売先の国にどの程度リスクがあるかの4つの観点で評価を行い、販売を承認するかどうかを決定するという。この他にも、顧客との契約の中で「当社製品を人権侵害に繋がるエンドユーザーに販売する可能性がある時には、誠実に話し合う場を設ける」等の文言を追加する等の措置が例として挙げられる。さらに、講じた防止/軽減措置の効果を検証するため、自社での情報収集のほか、顧客企業等との対話を行うことも有効だろう。
販売先での人権リスクが顕在化した場合に関係者が通報できる窓口等の設置も重要だ。既に自社従業員やサプライヤー向けの窓口やホットラインを設置している企業は少なくないが、こうした窓口を顧客企業の従業員や、顧客企業が自社製品・サービスを用いることで影響を受け得るその他のステークホルダーが利用できるようにすることが望ましい。例えば、デンマークの大手風力発電機企業のべスタス社は、建設会社を直接の顧客としているが、自社製品が建設会社によって設置される地域の周辺住民を対象とした窓口を設置している。風力発電機の運用により騒音等の悪影響を及ぼすことも「人権侵害」の一つであるため、何か問題があった際に周辺住民が気軽に通報できるよう、苦情申し立て用の専用ボックスを設置し、メモ用紙に意見を記入して入れられるようにしている。
「自社製品が紛争や弾圧に使われるリスク」を考慮せよ
企業にとって、全てのサプライヤーの状況を把握することが難しいのと同様、全ての販売先の状況を把握することも当然難しい。しかしもし仮に知らないうちに自社製品・サービスが紛争や弾圧に用いられている事実が明らかになった場合、「販売先の状況を把握する努力を一切していない」企業と「自らの影響力を行使して負の影響を防止・軽減するよう働きかけている」企業に向けられるステークホルダーの目は、大きく異なったものになるだろう。人権への取り組みを自社や原材料等を調達しているサプライヤーに限定している企業には、まずは「自社製品が紛争や弾圧に使われるリスクがあるかもしれない」という前提で、販売先の人権リスクも視野に入れて取り組みを見直すことが求められている。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
マネジャー
石井 麻梨
コンサルタント
玉井 仁和子